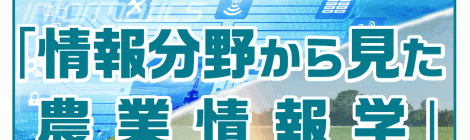
情報分野から見た農業情報学 近年、農業分野の研究においても、情報技術を活用することが当たり前になってきている。このため、農業分野の研究者も情報技術を使いこなすことが求められ、実際に一部の研究者は高度な情報技術を使いこな…

2022年度アグリコクーンガイダンス一覧 2022年度パンフレット 4月4日 Zoom開催 アグリコクーン全体ガイダンス(ゲスト:アグリバイオインフォマティクス/One Earth Guardians育成プログラム) 4…
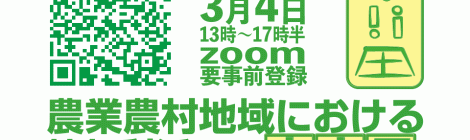
農学における情報利用研究フォーラムグループ 農業農村地域における情報利活用の未来図Ⅱ poster(PDF) 日時:2022年3月4日(金)13:00-17:30 場所: zoom 参加費: なし 主催:農業農村工学会・…
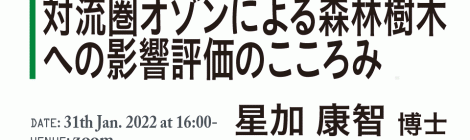
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 対流圏オゾンによる森林樹木への影響評価のこころみ poster(PDF) 講師:星加 康智 イタリア国立陸域生態系研究所 上席研究員 農学に…
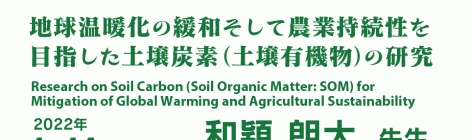
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 特別セミナー 地球温暖化の緩和そして農業持続性を目指した土壌炭素(土壌有機物)の研究 poster(PDF) 講師:和穎 朗太 先生 (エコロジカル・セイフティー学) ご関…
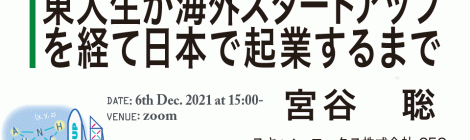
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 東大生が海外スタートアップを経て日本で起業するまで poster(PDF) 講師:宮谷 聡 スキャン・エックス株式会社 CEO compan…
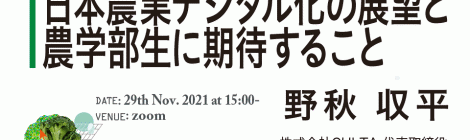
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 日本農業デジタル化の展望と農学部生に期待すること poster(PDF) 講師:野秋 収平 株式会社CULTA 代表取締役 CULTA(カル…
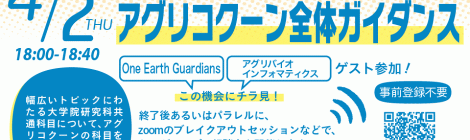
2021年度アグリコクーンガイダンス一覧 ガイダンスの動画をECCSアクセス限定で配信中 https://drive.google.com/file/d/1K4wM0MpjOKAmOkCitnQwt5JmICh7qJaS…
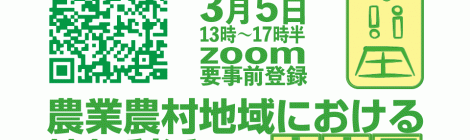
農学における情報利用研究フォーラムグループ 農業農村地域における情報利活用の未来図 poster(PDF) 日時:2021年3月5日(金)13:00-17:30 場所: zoom 参加費: なし 主催:農業農村工学会・農…
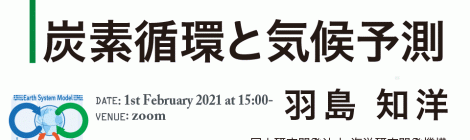
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 炭素循環と気候予測 poster(PDF) 講師:羽島 知洋 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 環境変動予測研究センター 地球システムモデ…










