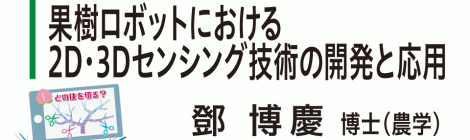
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 果樹ロボットにおける2D・3Dセンシング技術の開発と応用 poster(PDF) 講師:鄧 博慶 博士(農学) 国立研究開発法人 農業・食品…
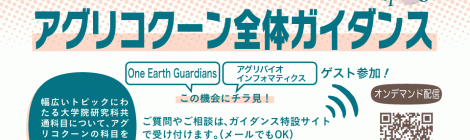
2025年度アグリコクーンガイダンス一覧 ガイダンス動画(youtube)、4月1日公開予定 2025年度パンフレット オンデマンド配信 アグリコクーン全体ガイダンス(ゲスト:アグリバイオインフォマティクス/One Ea…

農学における情報利用研究フォーラムグループ ChatGPTをプラットフォームにした災害復興知の活用 {仮題} poster(PDF) 日時:2025年3月31日(月) 15:00-17:00 場所: Zoom ミーティン…
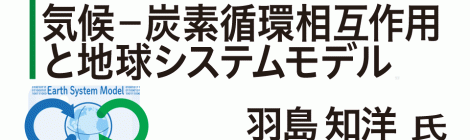
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 気候−炭素循環相互作用と地球システムモデル poster(PDF) 講師:羽島 知洋 氏 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 環境変動予測研…
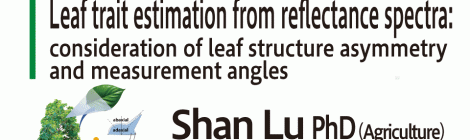
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール Leaf trait estimation from reflectance spectra: consideration of leaf …
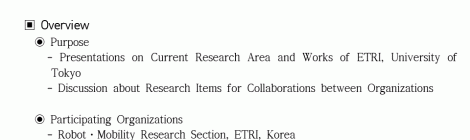
Agro-Informatics Forum Group 2024 Joint Workshop on Future Precision Agriculture Technology poster(PDF) date:T…
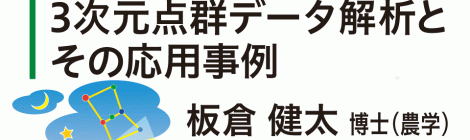
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 3次元点群データ解析とその応用事例 poster(PDF) 講師:板倉 健太 博士(農学) ImVisionLabs 代表取締役社長 農学に…
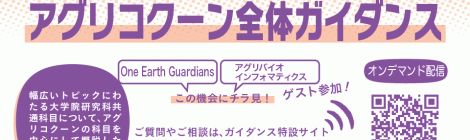
2024年度アグリコクーンガイダンス一覧 ガイダンス動画(youtube) 2024年度パンフレット オンデマンド配信 アグリコクーン全体ガイダンス(ゲスト:アグリバイオインフォマティクス/One Earth Guard…

農学における情報利用研究フォーラムグループ 農業農村地域における情報利活用の未来図Ⅳ 日時:2024年3月1日(金)13:00-17:00 場所: (対面)東京大学農学部2号館別館462号室 (オンライン)ミーティングI…
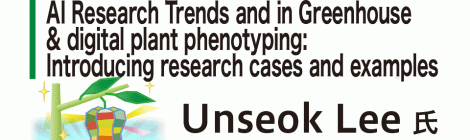
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール AI Research Trends and in Greenhouse & digital plant phenotyping:…










