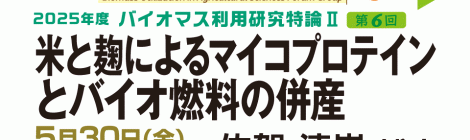
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 日時:2025年5月30日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 米と麹によるマイコプロテインとバイオ燃料の併産 講義: 佐賀 清崇 博士(Agro Ludens株式会社代表取締役) コーディネーター:古橋 賢一 助教 (生物・環境工学専攻 生物機械工学研究室) 食経験のある麹菌を活用して、動物性タンパク質を代替する「美味しく風味豊かな」マイコプロテインを残渣から食品としてアップサイクルしつつ、デンプン系やセルロース系バイオマス由来のバイオエタノール生産の経済性を上げる併産プロセスを紹介します。なお、佐賀先生は本研究科生物・環境工学専攻で博士号を取得されています。無駄なく環境に優しいバイオマス燃料と日本の伝統的発酵技術のフュージョンをお楽しみください。
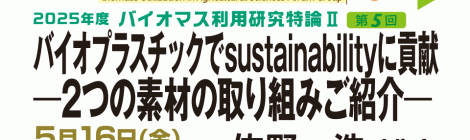
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 日時:2025年5月16日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 バイオプラスチックでsustainabilityに貢献 ―2つの素材の取り組みご紹介― 講義: 佐野 浩 博士(三菱ケミカルグループ株式会社 グリーントランスフォーメーション推進本部) コーディネーター:岩田 忠久 教授 (生物材料科学専攻専攻 森高分子材料学研究室) 成形加工が容易で軽量で耐久性にすぐれ安価便利なプラチック。プラスチックは暮らしの隅々にまで浸透しています。しかし、その利用と廃棄が拡大し続けるプラスチックは、私たちの暮らしにひとつの疑問符を投げかけています。今回は、2つのバイオプラスチックを市場に送り出してきた開発者の方に、持続可能な循環型社会の実現に貢献するバイオプラスチックとそのサプライチェーンを通した産業界の挑戦について伺います。
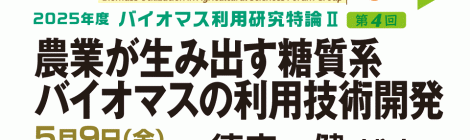
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 日時:2025年5月9日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 農業が生み出す糖質系バイオマスの利用技術開発 講義: 徳安 健 博士(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門・主席研究員/東京大学プラネタリーヘルス研究機構 特任教授/東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授(委嘱)) コーディネーター:五十嵐圭日子 教授 (生物材料科学専攻専攻 森林化学研究室) 農林水産業の生産現場で大量に生産される多糖資源。澱粉やセルロースはその代表です。そのうち、食卓にあがるなど有効活用されるのは一部で、生産・加工・流通の過程で多くの未利用資源が残ったままです。今回は、その研究キャリアの大半を糖質資源を対象とした高度利用研究に注いできた第一線の研究者にご講演いただき、水田や畑などで生み出される草本系糖質資源の高度利用、作物の炭素固定能力を生かした低・脱炭素、循環型農業の展望について伺います。
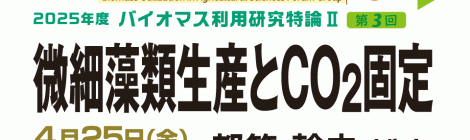
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 日時:2025年4月25日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 微細藻類生産とCO2固定 講義: 都筑 幹夫 博士(東京薬科大学生命科学部 名誉教授) コーディネーター:岡田 茂 教授 (水圏生物科学専攻 水圏天然物化学研究室) 光合成は地球上のほとんど全ての生物の存在を支えています。光独立栄養性の微細藻は、化石資源に替わる燃料やマテリアル原料として期待され、その大量培養の研究が進んでいますが、経済性、エネルギー収支、生産量が社会実装の壁として立ちはだかっています。演者は東京大学応用微生物研究所所属時以来、今日まで微細藻類の生理・生化学研究とその成果に基づいた新規固相表面連続培養法の開発に取り組んで来られました。光合成の可能性、微細藻類産業の今後の展望について知る絶好の機会です。
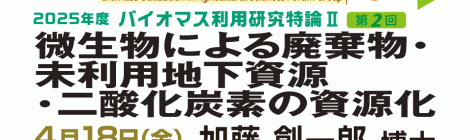
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 日時:2025年4月18日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 微生物による廃棄物・未利用地下資源・二酸化炭素の資源化 講義: 加藤 創一郎 博士(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 バイオものづくり研究センター 上級主任研究員) コーディネーター:新井 博之 准教授 (応用生命工学専攻 応用微生物学研究室) 微生物の無限ともいえるエネルギー代謝の多様性。微生物には未知の領域が多く残されています。今回のセミナーは新規代謝系の発見、分子機構の解明、および人為的制御を目指した研究開発を行う第一線の研究者をお呼びし、廃棄物や低質の未利用資源から有価値の資源を産み出す微生物のヒミツと魅力、新発見についてお話しいただきます。
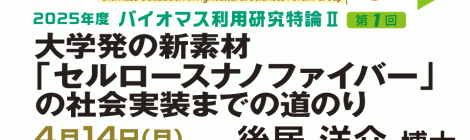
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 日時:2025年4月14日(月)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 大学発の新素材 「セルロースナノファイバー」 の社会実装までの道のり 講義: 後居 洋介 博士(第一工業製薬株式会社 京都中央研究所 コーポレート研究部 サステナブル材料グループ グループ長) コーディネーター:斎藤 継之 教授 (生物材料科学専攻 製紙科学研究室) セルロースナノファイバー(CNF)は、バイオマス由来の新規ナノ素材です。CNFは、すでに私たちの生活の身近なところで使われ始めていますが、その産業用途としての展開には、まだまだ課題が残っています。従来にない新しい特性と可能性をもった新素材の社会実装・実用化に携わった開発者にお話を伺います。ものづくりの楽しさ、大変さについて一緒に語りましょう。
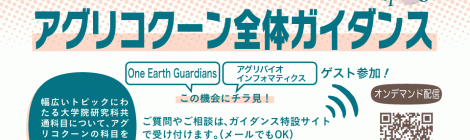
2025年度アグリコクーンガイダンス一覧 ガイダンス動画(youtube)、4月1日公開予定 2025年度パンフレット オンデマンド配信 アグリコクーン全体ガイダンス(ゲスト:アグリバイオインフォマティクス/One Earth Guardians育成プログラム) アグリコクーンの全体ガイダンスをオンデマンドで配信予定です. 今年度も,オープニングにアグリバイオインフォマティクスとOne Earth Guardians育成育成機構の先生をお招きし,各プログラムの紹介をします. (動画の作成にあたっては,生成AIを積極的に活用しています) TIME TABLE イントロダクション:研究科としての横断的教育プログラムの紹介 岩田 忠久 アグリバイオインフォマティクス 大森 良弘 One Earth Guardians育成プログラム 中西 もも アグリコクーン各FGの紹介 食の科学FG 八村 敏志 国際農業と文化FG 荒木 徹也 農学におけるバイオマス利用研究FG 岩田 忠久 生物多様性・生態系再生FG 吉田 丈人 農学における情報利用研究FG 細井 文樹 農における放射線影響FG 田野井 慶太朗 アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG) ◆食の科学フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の向上と豊かな社会の構築を目指します 食の安全・安心の確立と健康社会の構築をめぐる理論と実践を学びます。そこでは高齢社会における課題解決についても考えていきます。またフォーラムグループの教員もメンバーになっている「食の安全研究センター」と研究や教育の連携を図ります。教育カリキュラムでは専門性と学際性を重視して、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。「国際農業と文化ゼミナール」では 「環境と農業」 「農業と資源」 「経済と食品流通」の3つのテーマの集中講義と、教員とのディスカッションで農業と文化への理解を深めます。「国際農業と文化実習」では、国内実習により日本の農家と農村について体験的に理解を深めた上で、アジア途上国における実習により、地域における問題の把握やそれらの問題解決のためのプロジェクト形成について経験を積みます。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します バイオマスとは、生物が生産する循環可能な有機資源を意味しています。また、バイオマスは農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場あるいはそれらの下流に位置づけられる産業や社会の中に存在しています。 農学生命科学の研究分野の中で、これらのバイオマスの多面的で高い次元での有効利用、地域環境の保全などを視野にいれた利活用の実現に向けた教育と研究を推進することが、バイオマス利用研究FGの使命と言えます。この理念にのっとり、バイオマス利用研究FGが主催する講義では、セミナー、現場視察、さらに演習を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 生態系や生物多様性を再生する協働活動を進めます 生物多様性の保全や健全な生態系の再生は、さまざまな生態系サービス(自然の恵み)の提供を通して、地域社会の持続可能性に貢献するものです。地域における自然再生や生態系管理にとって、地域の多様な関係者との協働は大きな役割を持っており、さまざまな地域で実践活動が進んでいます。国内の先進的な事例をとりあげ、地域と連携した実習などにより、自然再生や生態系管理について実践的に学びます。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 最先端農業システムやリモートセンシング・地理空間情報、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う農業気象情報や食料需給問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催し、農業環境情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 福島第一原発事故による放射能汚染地域の大半は、農林畜水産業の場です。この被災地における農林畜水産業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科は事故直後からそのための調査研究を行っています。本FGでは、最新の知見や発見に基づく教育プログラムによって、農における放射性物質の動態や影響を学びます。本FGは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の育成を目指します。 ご質問 ご質問はコメント機能でおよせください。
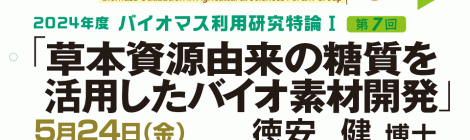
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅰ poster(PDF) 日時:2024年5月24日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 「草本資源由来の糖質を活用したバイオ素材開発」 講義: 徳安 健 博士(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門 食品加工・素材研究領域 バイオ素材開発グループ グループ長): 担当: 五十嵐圭日子 教授 (生物材料科学 森林化学研究室) 多糖資源は地球上の陸圏・水圏で大量に生産され巨大な炭素循環フローを形成します。地域で農林水産業などの副産物としても生産される多糖資源の高度利用は持続的社会の構築にとって重要です。今回は、その研究キャリアの大半を糖質資源を対象とした高度利用研究に注いできた第一線の研究者に、草本系資源由来の糖質を活用した「ものづくり」についてお話しいただきます。
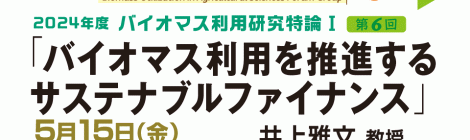
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅰ poster(PDF) 日時:2024年5月15日(水)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 「バイオマス利用を推進するサステナブルファイナンス」 講義: 井上 雅文 教授 (アジア生物資源環境研究センター) 長坂 健司 特任講師 (木材利用システム学寄付講座) 木材をはじめとするバイオマスはその材料特性から、その利用拡大によってグローバルな環境および社会問題の解決に貢献できます。そして、SDGsの達成に向けて、森と木材に注目する企業が増えています。 今回は、森とビジネスの関係がいまどうなっているか学んで討議します。
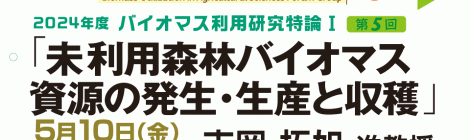
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅰ poster(PDF) 日時:2024年5月10日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 「未利用森林バイオマス資源の発生・生産と収穫」 講義: 吉岡 拓如 准教授 (森林科学専攻 森林利用学研究) 森林利用学では、木材の伐採・搬出からその利用まで、資源をより安全にかつ効率的に供給するプロセスを追究します。 現状、林地残材や未利用材の利用を促進することには多くの課題があります。 今回の講義では森林バイオマス利用について概説のうえ、未利用・低利用の森林バイオマスをどう効率的・経済的に収集するか、現状と課題を新技術の導入や可能性を含めて紹介・検討します。










