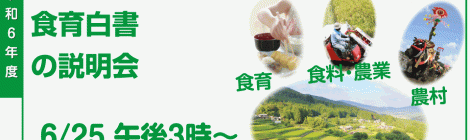
令和6年度 食料・農業・農村白書&食育白書の説明会 例年開催している「食料・農業・農村白書&食育白書の説明会」を今年度も開催します。 学部・専攻・専修問わずご参加いただけます。 令和6年度食料・農業・農業白書(概要) https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/pdf/r6_gaiyou_all.pdf 掲載ページ:令和6年度 食料・農業・農村白書(令和7年5月30日公表):農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/index.html プレスリリース:令和6年度食料・農業・農村白書を本日公表:農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo04/250530.html 令和6年度食育推進施策(食育白書)〔概要〕 【MV】NO FOOD,NO FUTURE!(食育のうた) poster(PDF) 日時:6月25日(水)15:00-16:30 場所:東京大学農学部8番講義室 主催:東京大学大学院農学生命科学研究科アグリコクーン食の科学FG(act158) プログラム 司会:上田 遥 (農業・資源経済学専攻 助教) 15:00-15:40 「食料・農業・農村白書」 大臣官房 広報評価課 15:40-16:00 「食育白書」 消費・安全局 消費者行政・食育課 16:00-16:30 質疑応答
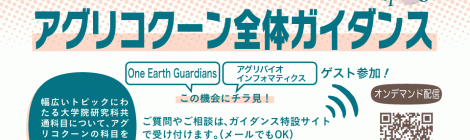
2025年度アグリコクーンガイダンス一覧 ガイダンス動画(youtube)、4月1日公開予定 2025年度パンフレット オンデマンド配信 アグリコクーン全体ガイダンス(ゲスト:アグリバイオインフォマティクス/One Earth Guardians育成プログラム) アグリコクーンの全体ガイダンスをオンデマンドで配信予定です. 今年度も,オープニングにアグリバイオインフォマティクスとOne Earth Guardians育成育成機構の先生をお招きし,各プログラムの紹介をします. (動画の作成にあたっては,生成AIを積極的に活用しています) TIME TABLE イントロダクション:研究科としての横断的教育プログラムの紹介 岩田 忠久 アグリバイオインフォマティクス 大森 良弘 One Earth Guardians育成プログラム 中西 もも アグリコクーン各FGの紹介 食の科学FG 八村 敏志 国際農業と文化FG 荒木 徹也 農学におけるバイオマス利用研究FG 岩田 忠久 生物多様性・生態系再生FG 吉田 丈人 農学における情報利用研究FG 細井 文樹 農における放射線影響FG 田野井 慶太朗 アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG) ◆食の科学フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の向上と豊かな社会の構築を目指します 食の安全・安心の確立と健康社会の構築をめぐる理論と実践を学びます。そこでは高齢社会における課題解決についても考えていきます。またフォーラムグループの教員もメンバーになっている「食の安全研究センター」と研究や教育の連携を図ります。教育カリキュラムでは専門性と学際性を重視して、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。「国際農業と文化ゼミナール」では 「環境と農業」 「農業と資源」 「経済と食品流通」の3つのテーマの集中講義と、教員とのディスカッションで農業と文化への理解を深めます。「国際農業と文化実習」では、国内実習により日本の農家と農村について体験的に理解を深めた上で、アジア途上国における実習により、地域における問題の把握やそれらの問題解決のためのプロジェクト形成について経験を積みます。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します バイオマスとは、生物が生産する循環可能な有機資源を意味しています。また、バイオマスは農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場あるいはそれらの下流に位置づけられる産業や社会の中に存在しています。 農学生命科学の研究分野の中で、これらのバイオマスの多面的で高い次元での有効利用、地域環境の保全などを視野にいれた利活用の実現に向けた教育と研究を推進することが、バイオマス利用研究FGの使命と言えます。この理念にのっとり、バイオマス利用研究FGが主催する講義では、セミナー、現場視察、さらに演習を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 生態系や生物多様性を再生する協働活動を進めます 生物多様性の保全や健全な生態系の再生は、さまざまな生態系サービス(自然の恵み)の提供を通して、地域社会の持続可能性に貢献するものです。地域における自然再生や生態系管理にとって、地域の多様な関係者との協働は大きな役割を持っており、さまざまな地域で実践活動が進んでいます。国内の先進的な事例をとりあげ、地域と連携した実習などにより、自然再生や生態系管理について実践的に学びます。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 最先端農業システムやリモートセンシング・地理空間情報、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う農業気象情報や食料需給問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催し、農業環境情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 福島第一原発事故による放射能汚染地域の大半は、農林畜水産業の場です。この被災地における農林畜水産業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科は事故直後からそのための調査研究を行っています。本FGでは、最新の知見や発見に基づく教育プログラムによって、農における放射性物質の動態や影響を学びます。本FGは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の育成を目指します。 ご質問 ご質問はコメント機能でおよせください。

「旬の鮭川木の子が大集合!」 山形県鮭川村の味覚を産地から出張販売!東大マルシェ@弥生 poster(PDF) 東京大学ホームカミングデーの一環として開催します 一般のかたもご自由に参加いただけます。 東京大学農学部が長年交流を続けてきた山形県最上郡鮭川村の特産品である6種類のきのこを販売します。その場で温かいきのこ汁、玉こんにゃくも味わえます。無形民俗文化財である「鮭川歌舞伎」の展示、そして隈取体験(歌舞伎メイク)も。今夏の豪雨被害からの復旧を願いながら、自然と文化が息づく鮭川村の魅力を感じてみませんか? 日時:2024年10月19日(土)9:30~15:00(売切次第終了) 場所:東京大学弥生キャンパス農正門横 農学資料館 アクセス: 主催:東京大学大学院農学生命科学研究科、 山形県鮭川村 後援:東京大学アグリコクーン教育・起業支援室(ACT 154) 問合せ:Tel: 03-5841-8882
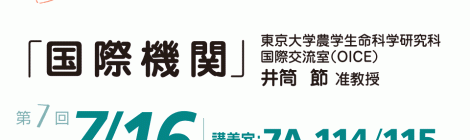
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 「国際機関」 日時:2024年7月16日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7A棟114/115講義室 講師: 東京大学農学生命科学研究科 国際交流室(OICE) 井筒 節 准教授 食の科学ゼミナールⅡ/食と健康システム演習では、農林水産業・食品産業に関する様々な領域において、官民の取組を紹介し、各専攻等において行われている研究がどのように社会に実装・還元されているかの実際を学びます。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。下記のフォームより登録してください。(要ECCSログイン)

食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 「水産資源管理・陸上養殖」 日時:2024年7月9日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7A棟114/115講義室 講師: 水産庁 資源管理部漁獲管理官 課長補佐 松島 博英 氏 株式会社FRDジャパン 代表取締役CCO 十河 哲朗 氏 食の科学ゼミナールⅡ/食と健康システム演習では、農林水産業・食品産業に関する様々な領域において、官民の取組を紹介し、各専攻等において行われている研究がどのように社会に実装・還元されているかの実際を学びます。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。下記のフォームより登録してください。(要ECCSログイン)

食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 「木材利用」 日時:2024年7月2日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7A棟114/115講義室 講師: 林野庁 木材利用課 課長 難波 良多 氏 株式会社竹中工務店 経営企画室 サステナビリティ推進部 小林 道和 氏 食の科学ゼミナールⅡ/食と健康システム演習では、農林水産業・食品産業に関する様々な領域において、官民の取組を紹介し、各専攻等において行われている研究がどのように社会に実装・還元されているかの実際を学びます。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。下記のフォームより登録してください。(要ECCSログイン)
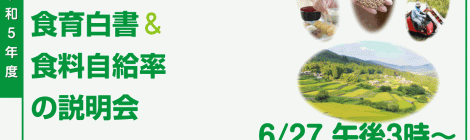
令和5年度 食料・農業・農村白書&食育白書&食料自給率の説明会 例年開催している「食料・農業・農村白書&食育白書&食料自給率の説明会」を今年度も開催します。 学部・専攻・専修問わずご参加いただけます。 1)令和5年度 食育白書(6/7公表) https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/r5_index.html 2)令和4年度 食料・農業・農村白書(5/31公表) https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r5/index.html poster(PDF) 日時:6月27日(木)15:00-16:30 場所:東京大学農学部8番講義室 主催:東京大学大学院農学生命科学研究科アグリコクーン食の科学FG(act152) プログラム 司会:八木 洋憲 (農業・資源経済学専攻 准教授) 「食料・農業・農村白書」 大臣官房 広報評価課 情報分析室長 牧之瀬 泰志 氏 「食育白書」 消費・安全局 消費者行政・食育課 課長補佐(食育白書担当)田中 早苗 氏 「食料自給率」 大臣官房 政策課 食料安全保障室 企画官(食料自給率担当)井坂 友美 氏 終了後、農林水産省業務説明会を開催します 於:10番講義室(16:50~18:35予定)
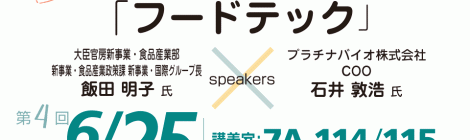
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 「フードテック」 日時:2024年6月25日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7A棟114/115講義室 講師: 大臣官房新事業・食品産業部 新事業・食品産業政策課 新事業・国際グループ長 飯田 明子 氏 プラチナバイオ株式会社 COO 石井 敦浩 氏 食の科学ゼミナールⅡ/食と健康システム演習では、農林水産業・食品産業に関する様々な領域において、官民の取組を紹介し、各専攻等において行われている研究がどのように社会に実装・還元されているかの実際を学びます。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。下記のフォームより登録してください。(要ECCSログイン)
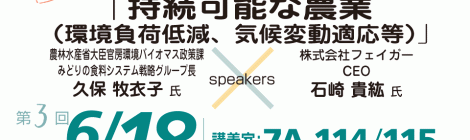
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 「持続可能な農業 (環境負荷低減、気候変動適応等)」 日時:2024年6月18日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7A棟114/115講義室 講師: 農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課 みどりの食料システム戦略グループ長 久保 牧衣子 氏 株式会社フェイガー CEO 石崎 貴紘 氏 食の科学ゼミナールⅡ/食と健康システム演習では、農林水産業・食品産業に関する様々な領域において、官民の取組を紹介し、各専攻等において行われている研究がどのように社会に実装・還元されているかの実際を学びます。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。下記のフォームより登録してください。(要ECCSログイン)
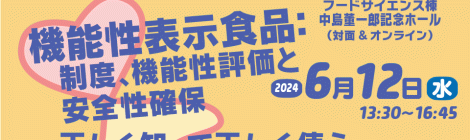
東京大学大学院農学生命科学研究科附属食の安全研究センターシンポジウム 「機能性表示食品:制度、機能性評価と安全性確保~正しく知って正しく使う~」 今年3月、「サプリメント」が原因とみられる健康被害の発生が厚生労働省から発表されました。現在のところ、この健康被害の原因となった成分や経緯の詳細は明らかになっていませんが、原因となったサプリメントが「機能性表示食品」であったことから、機能性表示食品をめぐる制度や機能性評価や安全性確保の方法など、様々な問題点が指摘されています。 一方で、「サプリメント」は医薬品と同等(または類似)の成分を高用量で摂取可能であるにもかかわらず「食品」であって医薬品のような規制を受けないことや「機能性表示食品」とはどのような制度であるのか、などについて正しく理解されていないと思われる報道や議論も多く目にします。 本シンポジウムでは、「食品の機能性」を有効かつ安全に利用するという原点に立ち戻り、「機能性表示食品」の機能性評価と安全性確保の方法、制度の課題やあり方などを議論し、「食の安全」を確保しながら「食品の機能性」を正しく活用する方法を考えていきます。 poster 日時:2024年6月12日(水)13:30〜16:45 場所:東京大学農学部フードサイエンス棟 中島董一郎記念ホール(オンライン配信有)オンライン参加の方でまだメールが届いていない場合は、正しいメールアドレスで再度お申し込みください。 主催:東京大学大学院農学生命科学研究科附属食の安全研究センター 後援:国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科アグリコクーン(act151) 参加費・申込:参加費無料/要事前登録 ※申込みはこちら(googleフォーム) イベントは無事終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。 要旨集: 【PDF download】 プログラム: 13:30-13:45 「初めに:機能性表示食品と保健機能食品制度」 平山和宏 (東京大学) 13:45-14:15 「機能性表示食品の機能性を示す」 八村敏志 (東京大学) 14:15-14:45 「ELSIの観点から食品の機能と安全を再考する」 喜田 聡 (東京大学) 14:45-15:15 「機能性表示食品の安全性確保 (令和6年通知に関して)」 穐山 浩 (星薬科大学) 15:30-16:00 「機能性表示食品の課題と未来」 清水 誠 (東京大学名誉教授) 16:00-16:45 総合討論 お問い合わせ先 東京大学大学院農学生命科学研究科附属食の安全研究センター e-mail: shokuhin[at]frc.a.u-tokyo.ac.jp (電話やFAXはアグリコクーンまで) tel: 03-5841-8882 fax: 03-5841-8883 information: http://www.frc.a.u-tokyo.ac.jp/information/240612.html










