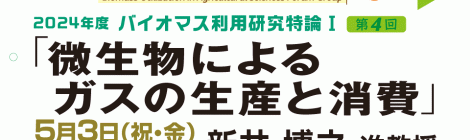
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅰ poster(PDF) 日時:2024年5月3日(祝・金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 「微生物によるガスの生産と消費」 講義: 新井 博之 准教授 (応用生命工学専攻 応用微生物学研究室) 各種代謝機能を有する微生物や微生物集団は、各種環境において地球上の物質循環に大きく関わっており、その働きは地球環境全体に大きな影響を与えています。大気を構成するガスの殆どは、微生物による変換(生産や消費)を受けます。 そして、こうした変換はバイオマスの有効利用にも密接に関わっています。 本講義では、バイオマスの有効利用に関わる微生物代謝なかでもガス代謝を概観します。
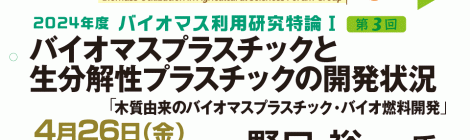
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅰ poster(PDF) 日時:2024年4月26日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 「バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの開発状況」 講義: 「バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの説明」 岩田 忠久 教授(生物材料科学専攻 高分子材料学研究室): 「木質由来のバイオマスプラスチック・バイオ燃料開発」 野口 裕一 氏 (王子ホールディングス株式会社 上級研究員) バイオマス素材を採用していく動きが世界の産業界で広がっています。 バイオマスプラスチックなど樹脂のバイオ化が進むにつれ、生分解性プラスチックにも注目が集まっています。食料と競合しないバイオ由来の 持続可能な燃料の開発も必要です。 今回のセミナーは「紙づくり」と「森づくり」のコア技 術を生かし、「木質由来の新素材」の開発にとりくむ王子ホールディングスから講師をお招きし、バイオ燃料の開発も含めて、グリーンイノベーションのフロンティアのお話を伺い、討議します。
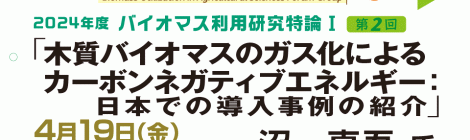
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅰ poster(PDF) 日時:2024年4月19日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 「木質バイオマスのガス化によるカーボンネガティブエネルギー: 日本での導入事例の紹介」 講義: 沼 真吾 氏 (フォレストエナジー株式会社 代表取締役社長) コーディネーター: 古橋 賢一 助教 (生物・環境工学専攻 生物機械工学研究室) 木質バイオマスをガス化させて電気と熱をとりだすガス化発電は、施設を大型化しなくても高い発電効率・熱効率を得られる、分散型のコジェネレーションシステムです。そのエコと効率性を両立させたソリューションは炭素排出削減とエネルギーの地産地消を目指すことを可能にします。 本セミナーでは、日本でのバイオマスガス化発電の導入事例について紹介いただき、地域の暮らしと産業を支えていくバイオマスエネルギーの展望について討議します。
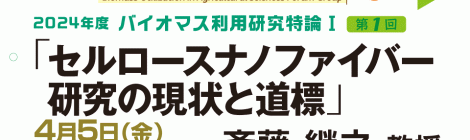
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅰ poster(PDF) 日時:2024年4月5日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 「セルロースナノファイバー研究の現状と道標」 講義: 斎藤 継之 教授 (生物材料科学専攻 製紙科学研究室) セルロースナノファイバー(CNF)は、新素材として様々な商品に採用されいますが、工業用途の産業資材としては未だ謎が多い素材です。社会実装のさらなる進展には、CNFの原子レベルでの制御などの基礎研究を積み上げる必要があります。本講義では、CNFの今後の展開に向けた研究課題・研究事例を紹介します。 この授業でセルロースのことがもっと面白くなります。
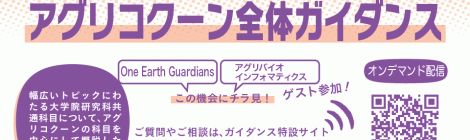
2024年度アグリコクーンガイダンス一覧 ガイダンス動画(youtube) 2024年度パンフレット オンデマンド配信 アグリコクーン全体ガイダンス(ゲスト:アグリバイオインフォマティクス/One Earth Guardians育成プログラム) アグリコクーンの全体ガイダンスをオンデマンド(youtube)で配信中です. 今年は,オープニングにアグリバイオインフォマティクスとOne Earth Guardians育成育成機構の先生をお招きし,各プログラムの紹介をします. (動画の作成にあたっては,生成AIを積極的に活用しています) TIME TABLE イントロダクション:研究科としての横断的教育プログラムの紹介 溝口 勝 アグリバイオインフォマティクス 大森 良弘 One Earth Guardians育成プログラム 高橋 伸一 アグリコクーン各FGの紹介 食の科学FG 八村 敏志 国際農業と文化FG 溝口 勝 農学におけるバイオマス利用研究FG 岩田 忠久 生物多様性・生態系再生FG 吉田 丈人 農学における情報利用研究FG 細井 文樹 農における放射線影響FG 田野井 慶太朗 アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG ◆食の科学フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の向上と豊かな社会の構築を目指します 食の安全・安心の確立と健康社会の構築をめぐる理論と実践を学びます。そこでは高齢社会における課題解決についても考えていきます。またフォーラムグループの教員もメンバーになっている「食の安全研究センター」と研究や教育の連携を図ります。教育カリキュラムでは専門性と学際性を重視して、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。「国際農業と文化ゼミナール」では 「環境と農業」 「農業と資源」 「経済と食品流通」の3つのテーマの集中講義と、教員とのディスカッションで農業と文化への理解を深めます。「国際農業と文化実習」では、国内実習により日本の農家と農村について体験的に理解を深めた上で、アジア途上国における実習により、地域における問題の把握やそれらの問題解決のためのプロジェクト形成について経験を積みます。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します バイオマスとは、生物が生産する循環可能な有機資源を意味しています。また、バイオマスは農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場あるいはそれらの下流に位置づけられる産業や社会の中に存在しています。 農学生命科学の研究分野の中で、これらのバイオマスの多面的で高い次元での有効利用、地域環境の保全などを視野にいれた利活用の実現に向けた教育と研究を推進することが、バイオマス利用研究FGの使命と言えます。この理念にのっとり、バイオマス利用研究FGが主催する講義では、セミナー、現場視察、さらに演習を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 生態系や生物多様性を再生する協働活動を進めます 生物多様性の保全や健全な生態系の再生は、さまざまな生態系サービス(自然の恵み)の提供を通して、地域社会の持続可能性に貢献するものです。地域における自然再生や生態系管理にとって、地域の多様な関係者との協働は大きな役割を持っており、さまざまな地域で実践活動が進んでいます。国内の先進的な事例をとりあげ、地域と連携した実習などにより、自然再生や生態系管理について実践的に学びます。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 最先端農業システムやリモートセンシング・地理空間情報、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う農業気象情報や食料需給問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催し、農業環境情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 福島第一原発事故による放射能汚染地域の大半は、農林畜水産業の場です。この被災地における農林畜水産業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科は事故直後からそのための調査研究を行っています。本FGでは、最新の知見や発見に基づく教育プログラムによって、農における放射性物質の動態や影響を学びます。本FGは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の育成を目指します。 ご質問 ご質問はコメント機能でおよせください。
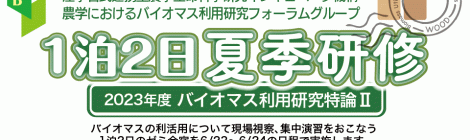
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 2023年度 1泊2日夏季研修:バイオマス利活用現場の視察、現地セミナーと集中討議 バイオマスの利活用について現場視察、集中演習をおこなう 1泊2日のゼミ合宿を6/23〜6/24の日程で実施します。 現場を視察して木質系バイオマスを中心に利活用の理解を深めます。 日時:2023年6月23日(金)〜6月24日(土) 訪問先:群馬県・埼玉県西部 集合時間:6/23 朝 農学部3号館前(午前9時集合) 参加費:学生は1万円(参加費には宿泊代、見学料,懇親会費、夕食代、朝食代、保険料が含まれます。) 視察先 フォレストエナジー株式会社 渋川バイオマス研究所
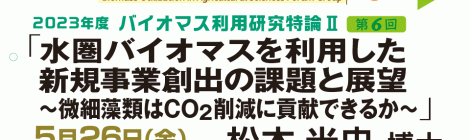
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論ⅠⅠ poster(PDF) 日時:2023年5月26日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 「水圏バイオマスを利用した新規事業創出の課題と展望 ~微細藻類はCO2削減に貢献できるか~」 講義: 松本 光史 氏 (株式会社クボタ グローバル技術研究所 次世代技術研究ユニット 次世代研究第三部 バイオチーム) コーディーター: 岡田 茂 准教授 (水圏生物科学専攻 水圏天然物化学研究室) 微細藻は脂肪酸や生物活性化合物、水素、多糖類など様々な有用物質を光合成でつくることができます。脂質を多く含む微細藻から代替燃料を作ることで炭素排出削減に貢献することも期待されています。微細藻類由来のグリーンオイル生産によって温室効果ガス排出削減を達成するには、経済性をクリアしつつ、低エネルギー、低CO2排出型の培養・生産プロセスを確立することが必要です。また、微細藻はカーボンリサイクルの手段としても注目されており、微細藻自体の生産性を高める研究開発も進んでいます。 様々なポテンシャルを秘めた微細藻を新規事業創出につなげるにはどんな課題があるのか、一緒に考えましょう。
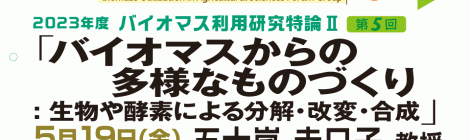
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論ⅠⅠ poster(PDF) 日時:2023年5月19日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 「バイオマスからの多様なものづくり:生物や酵素による分解・改変・合成」 講義: 五十嵐圭日子 教授 (生物材料科学専攻 森林化学研究室) きのこや酵素の力を借りて、色々なバイオマスから色々なものをつくる森林化学研究室の五十嵐先生にご講義いただきます。低いエネルギー投入で環境負荷の低い新しいマテリアルをつくる研究の楽しさに誘います。 五十嵐先生のインタビュー記事が公開されていますので、こちらもご覧ください。 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/features/z0405_00007.html
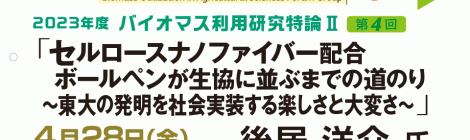
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論ⅠⅠ poster(PDF) 日時:2023年4月28日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 「セルロースナノファイバー配合ボールペンが生協に並ぶまでの道のり ~東大の発明を社会実装する楽しさと大変さ~」 講義: 後居 洋介 氏 (第一工業製薬株式会社 研究本部・研究カンパニー部 レオクリスタル開発グループ長) コーディネーター: 齋藤 継之 教授 (生物材料科学専攻 製紙科学研究室) セルロースナノファイバー(CNF)は、バイオマス由来の新規ナノ素材です。CNFは開発途上の素 材ですが、すでに私たちの生活の身近なところで使われ始めています。その一つの例が東大生協でも販売されているボールペンです。従来にない新しい特性と可能性をもった新素材の社会実装・実用化に携わった開発者にお話を伺います。ものづくりの楽しさ、大変さについて一緒に語りましょう。
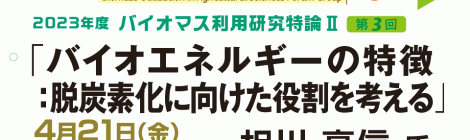
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論ⅠⅠ poster(PDF) 日時:2023年4月21日(金)16:50〜18:35 教室:1号館7番講義室 「バイオエネルギーの特徴 :脱炭素化に向けた役割を考える」 講義: 相川 高信 氏 (公益財団法人自然エネルギー財団 上級研究員) コーディネーター: 芋生 憲司 教授 (生物・環境工学専攻 生物機械工学研究室) IPCCは1.5度目標実現への窓を閉ざさないため、2035年までに二酸化炭素排出量を2019年比で65%削減することを世界に求めています。エネルギーの脱炭素化を実現するためには、自然エネルギー拡大の可能性を今以上に追求することが必要になると考えられます。バイオエネルギーは多様な自然エネルギー構成のなかでどんな役割をもつのか、その特性とポテンシャル含めて一緒に考えましょう。










