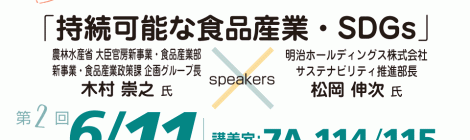
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 持続可能な食品産業・SDGs 日時:2024年6月11日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7A…

食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 知的財産を活用したビジネス 日時:2024年6月4日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7A棟1…
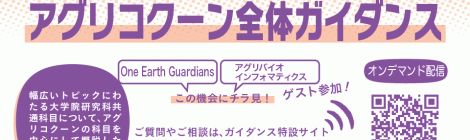
2024年度アグリコクーンガイダンス一覧 ガイダンス動画(youtube) 2024年度パンフレット オンデマンド配信 アグリコクーン全体ガイダンス(ゲスト:アグリバイオインフォマティクス/One Earth Guard…

公開シンポジウム 「食料自給率の動向と見通し-食料・農業・農村基本法改正に向けて」 食料・農業・農村基本法の改正法案が2024年通常国会に提出され審議される予定である。現行食料・農業・農村基本法では、食料自給率の目標を掲…
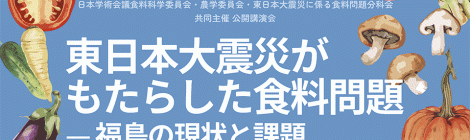
公開シンポジウム 「東日本大震災がもたらした食料問題-福島県の現状と課題-」 poster オンライン参加申込(外部リンク):http://www.academy-nougaku.jp/symposium.html 日時…
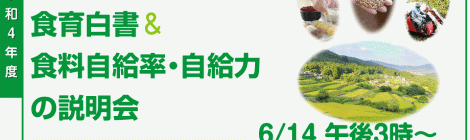
令和4年度 食料・農業・農村白書&食育白書&食料自給率・自給力の説明会 例年開催している「食料・農業・農村白書&食育白書&食料自給率・自給力の説明会」を今年度もハイブリッドで開催します。今年度は、基本法の検証・見直しにつ…
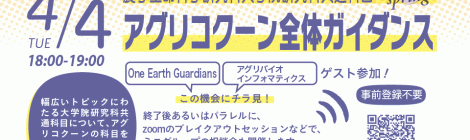
2023年度アグリコクーンガイダンス一覧 2023年度パンフレット 4月4日 Zoom開催 アグリコクーン全体ガイダンス(ゲスト:アグリバイオインフォマティクス/One Earth Guardians育成プログラム) 4…
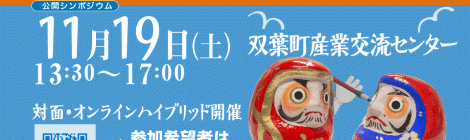
公開シンポジウム 「東日本大震災に係る食料問題フォーラム2022-原子力災害11年の総括と福島県農林水産業の復興-」 開催趣旨: 東日本大震災・原発事故から11年半が経過した。原子力災害を経験した福島県、特に浜通りの地域…
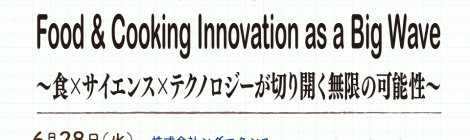
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) Food & Cooking Innovation as a Big Wave ~食×サイエ…
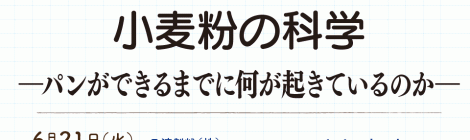
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 小麦粉の科学―パンができるまでに何が起きているのか― 日時:2022年6月21日(火)19:00〜20…










