
2018年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月5日(木)18:45~ 1号館2階8番講義室 FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月4日(水)18:15~19:00 7号館B棟231・232号室 FG3: 農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ4月6日(金)16:50~ 2号館1階化学2講義室 FG4: 生物多様性・生態系再生フォーラムグループ6月5日(火)13:30〜15:00 2号館1階化2講義室 FG5: 農学における情報利用研究フォーラムグループ 4月5日(木)16:50~17:307号館A棟7階会議室 FG6: 農における放射線影響フォーラムグループ4月9日(月)18:45~ 2号館1階化3講義室 Writing a Research Proposal / Writing a Research Article 3月30日(金)13:00〜4月4日(水)16:00〜 7号館B棟236/2377号館B棟 231/232 アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG) ◆食の科学フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の向上と豊かな社会の構築を目指します 食の安全・安心の確立と健康社会の構築をめぐる理論と実践を学びます。そこでは高齢社会における課題解決についても考えていきます。またフォーラムグループの教員もメンバーになっている「食の安全研究センター」と研究や教育の連携を図ります。教育カリキュラムでは専門性と学際性を重視して、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。「国際農業と文化ゼミナール」では 「環境と農業」 「農業と資源」 「経済と食品流通」の3つのテーマの集中講義と、教員とのディスカッションで農業と文化への理解を深めます。「国際農業と文化実習」では、国内実習により日本の農家と農村について体験的に理解を深めた上で、アジア途上国における実習により、地域における問題の把握やそれらの問題解決のためのプロジェクト形成について経験を積みます。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します バイオマスとは、生物が生産する循環可能な有機資源を意味しています。また、バイオマスは農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場あるいはそれらの下流に位置づけられる産業や社会の中に存在しています。 農学生命科学の研究分野の中で、これらのバイオマスの多面的で高い次元での有効利用、地域環境の保全などを視野にいれた利活用の実現に向けた教育と研究を推進することが、バイオマス利用研究FGの使命と言えます。この理念にのっとり、バイオマス利用研究FGが主催する講義では、セミナー、現場視察、さらに演習を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 環境を再生する協働活動を進めます 当FGは、2003年に21世紀COEプログラムの一環で立ち上げられた「生物多様性・生態系再生研究拠点」をベースにしています。さまざまな主体との協働プロジェクトやセミナーの開催などの実績があり、その成果を教育プログラムに還元するとともに、生物多様性とその保全に関わる学際的な新しい科学の創造を目指します。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 最先端農業システムやリモートセンシング・地理空間情報、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う農業気象情報や食料需給問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催し、農業環境情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 福島第一原発事故による放射能汚染地域の大半は、農林畜水産業の場です。この被災地における農林畜水産業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科は事故直後からそのための調査研究を行っています。本FGでは、最新の知見や発見に基づく教育プログラムによって、農における放射性物質の動態や影響を学びます。本FGは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の育成を目指します。
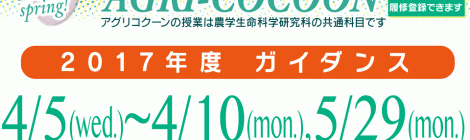
2017年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月6日(木)18:45~ 1号館2階8番講義室 FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月5日(水)18:15~19:00 7号館B棟231・232号室 FG3: 農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ4月7日(金)16:50~ 2号館1階化学2講義室 FG4: 生物多様性・生態系再生フォーラムグループ5月29日(月)13:30〜15:00 2号館1階化2講義室 FG5: 農学における情報利用研究フォーラムグループ 4月10日(月)18:00~18:302号館1階化3講義室 FG6: 農における放射線影響フォーラムグループ4月10日(月)18:45~ 2号館1階化3講義室 アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG) ◆食の科学フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の向上と豊かな社会の構築を目指します 食の安全・安心の確立と健康社会の構築をめぐる理論と実践を学びます。そこでは高齢社会における課題解決についても考えていきます。またフォーラムグループの教員もメンバーになっている「食の安全研究センター」と研究や教育の連携を図ります。教育カリキュラムでは専門性と学際性を重視して、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。「国際農業と文化ゼミナール」では 「環境と農業」 「農業と資源」 「経済と食品流通」の3つのテーマの集中講義と、教員とのディスカッションで農業と文化への理解を深めます。「国際農業と文化実習」では、国内実習により日本の農家と農村について体験的に理解を深めた上で、アジア途上国における実習により、地域における問題の把握やそれらの問題解決のためのプロジェクト形成について経験を積みます。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します バイオマスとは、生物が生産する循環可能な有機資源を意味しています。また、バイオマスは農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場あるいはそれらの下流に位置づけられる産業や社会の中に存在しています。 農学生命科学の研究分野の中で、これらのバイオマスの多面的で高い次元での有効利用、地域環境の保全などを視野にいれた利活用の実現に向けた教育と研究を推進することが、バイオマス利用研究FGの使命と言えます。この理念にのっとり、バイオマス利用研究FGが主催する講義では、セミナー、現場視察、さらに演習を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 環境を再生する協働活動を進めます 当FGは、2003年に21世紀COEプログラムの一環で立ち上げられた「生物多様性・生態系再生研究拠点」をベースにしています。さまざまな主体との協働プロジェクトやセミナーの開催などの実績があり、その成果を教育プログラムに還元するとともに、生物多様性とその保全に関わる学際的な新しい科学の創造を目指します。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 最先端農業システムやリモートセンシング・地理空間情報、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う農業気象情報や食料需給問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催し、農業環境情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 福島第一原発事故による放射能汚染地域の大半は、農林畜水産業の場です。この被災地における農林畜水産業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科は事故直後からそのための調査研究を行っています。本FGでは、最新の知見や発見に基づく教育プログラムによって、農における放射性物質の動態や影響を学びます。本FGは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の育成を目指します。
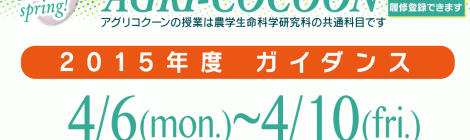
2015年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月7日(火)18:45~ 1号館2階8番講義室 FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月8日(水)17:00~18:00 7号館B棟231・232号室 FG3: 農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ4月10日(金)16:50~ 2号館1階化学2番講義室 FG4: 生物多様性・生態系再生フォーラムグループガイダンスは実施しません。全体ガイダンスで資料を配布します。 FG5: 農学における情報利用研究フォーラムグループ 4月8日(水)16:00~16:307号館B棟231・232号室 FG6: 農における放射線影響フォーラムグループ4月6日(月)18:45~20:30 2号館1階化3講義室 アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG) ◆食の科学フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の向上と豊かな社会の構築を目指します 食の安全・安心の確立と健康社会の構築をめぐる理論と実践を学びます。そこでは高齢社会における課題解決についても考えていきます。例年、講義・演習・実習には100名以上の学生が参加しています。またフォーラムグループの教員もメンバーになっている「食の安全研究センター」と研究と教育の連携を図ります。教育カリキュラムでは専門性と学際性を重視して、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を、地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。6つのサブグループ:「土と文化」「森と文化」「水と文化」「生き物と文化」「農業技術と文化」「プロジェクト実践研修」から成り、各サブグループの活動を、大学院生が中心となって企画・運営します。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します 生物が生産する有機資源であるバイオマスは、農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場に存在しています。バイオマスの高い次元での有効利用、地球環境の持続性を視野に入れたバイオマス利活用で、農学生命科学の研究分野の大きな使命である真の循環社会の構築を目指します。当フォーラムグループでは、この理念にのっとり、バイオマス利活用の現場視察を含むセミナー形式の講義とバイオマス利活用に必要な情報科学に関する演習を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 環境を再生する協働活動を進めます 当FGは、2003年に21世紀COEプログラムの一環で立ち上げられた「生物多様性・生態系再生研究拠点」をベースにしています。さまざまな主体との協働プロジェクトやセミナーの開催などの実績があり、その成果を教育プログラムに還元するとともに、生物多様性とその保全に関わる学際的な新しい科学の創造を目指します。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 最先端農業システムやリモートセンシング・地理空間情報、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う農業気象情報や食料需給問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催し、農業環境情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 放射能汚染地域の大半は農林畜水産業の場です。被災地での農業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科では事故直後から調査研究を行っています。そこで得られた最新の知見や発見に基づく教育プログラムを通じて、農における放射性物質動態・影響を学びます。本FGでは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の輩出を目指します。

2013年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1:食の安全・安心フォーラムグループ4月11日(木)18:30 1号館2階8番講義室 FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月10日(水)17:00 7号館B棟231・232号室 FG3: 農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ4月5日(金)16:00 2号館化学1番講義室 FG4: 生物多様性・生態系再生フォーラムグループガイダンスは実施しません。全体ガイダンスで資料を配布します。 FG5: 農学における情報利用研究フォーラムグループ 4月5日(金)アグリバイオインフォマティクス・ガイダンス終了後開始 2号館化1講義室 FG6: 農における放射線影響フォーラムグループ4月8日(金)18:30 1号館2階8番講義室 アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG) ◆食の安全・安心フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の再構築を目指します 食の安全・安心をめぐる理論と実践を学びます。例年、講義・演習・実習には100名以上の学生が参加しています。また2006年度に発足した「食の安全研究センター」とも連携しながら、数々の国際シンポジウムを主催・共催しています。専門性と学際性を兼ね備えた教育カリキュラムでは、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を、地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。6つのサブグループ:「土と文化」「森と文化」「水と文化」「生き物と文化」「農業技術と文化」「プロジェクト実践研修」から成り、各サブグループの活動を、大学院生が中心となって企画・運営します。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します バイオマスは、農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場に存在しています。生物資源の高い次元での有効利用、地球環境の保全などを視野に入れたバイオマスの利活用は、農学生命科学の研究分野の大きな使命である―当FGはこの理念にのっとり、講義と現場視察を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 環境を再生する協働活動を進めます 当FGは、2003年に21世紀COEプログラムの一環で立ち上げられた「生物多様性・生態系再生研究拠点」をベースにしています。さまざまな主体との協働プロジェクトやセミナーの開催などの実績があり、その成果を教育プログラムに還元するとともに、生物多様性とその保全に関わる学際的な新しい科学の創造を目指します。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 食の安全・安心に関連するトレーサビリティ、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う水循環変動や食料需給の問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催しフィールド情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 放射能汚染地域の大半は農林畜水産業の場です。被災地での農業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科では事故直後から調査研究を行っています。そこで得られた最新の知見や発見に基づく教育プログラムを通じて、農における放射性物質動態・影響を学びます。本FGでは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の輩出を目指します。

平成24年度 アグリコクーン ガイダンス一覧 FG1:食の安全・安心フォーラムグループ4月5日(木)18:30 1号館2階8番講義室 FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月5日(木)17:00 7号館B棟231・232号室 FG3: 農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ4月6日(金)17:00 2号館化学3番講義室 FG4: 生物多様性・生態系再生フォーラムグループ4月5日(木)18:00 1号館8番講義室 FG5: 農学における情報利用研究フォーラムグループ 4月5日(木)17:307号館B棟231・232号室 アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG) ◆食の安全・安心フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の再構築を目指します 食の安全・安心をめぐる理論と実践について学びます。昨年度の講義・演習・実習には100名以上の学生が参加しました。また平成18年度に開設された「食の安全研究センター」とも連携しながら、数々の国際シンポジウムを主催・共催しています。専門性と学際性を兼ね備えた教育カリキュラムでは、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を、地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。6つのサブグループ:「土と文化」「森と文化」「水と文化」「生き物と文化」「農業技術と文化」「プロジェクト実践研修」から成り、各サブグループの活動を、大学院生が中心となって企画・運営します。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します バイオマスは、農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場に存在しています。生物資源の高い次元での有効利用、地球環境の保全などを視野に入れたバイオマスの利活用は、農学生命科学の研究分野の大きな使命である――当FGはこの理念にのっとり、講義と現場視察を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 環境を再生する協働活動を進めます 当FGは、2003年に21世紀COEプログラムの一環で立ち上げられた「生物多様性・生態系再生研究拠点」をベースにしています。さまざまな主体との協働プロジェクトやセミナーの開催などの実績があり、その成果を教育プログラムに還元するとともに、生物多様性とその保全に関わる学際的な新しい科学の創造を目指します。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 食の安全・安心に関連するトレーサビリティ、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う水循環変動や食料需給の問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催しフィールド情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 放射能汚染地域の大半は農林畜産業の場です。被災地での農業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科では事故直後から調査研究を行っています。そこで得られた最新の知見や発見に基づく教育プログラムを通じて、農における放射性物質動態・影響を学びます。本FGでは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の輩出を目指します(平成24年度は授業は実施しませんが、勉強会やシンポジウム等を企画しています)。

シンポジウム「生物多様性と農業」(ACT22) 日時:2007年11月17日(土)13:00~17:40 場所:東京大学農学部弥生講堂 一条ホール アグリコクーン生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 平成19年度 冬学期 農学生命科学研究科 大学院 共通科目(演習:1単位) 「生物多様性と農業」履修案内 経済性と効率のみの追求による農業形態の変化の中で、急速に不健全化を進めた農業生態系。 その中で、社会と生態系を再生し、自然と調和のとれた人間社会を築こうとする流れは、世界的潮流である。日本でもその萌芽が見られはじめている。2005年9月、兵庫県豊岡市において、農業生態系の頂点に位置する「コウノトリ」が野生復帰に向けて放鳥された。3年目を迎える今年は、43年ぶりに自然状態で誕生したヒナが無事に巣立ちを迎えている。 これらの取組みの中核を担うのが、生物多様性の保全と矛盾しない新しい農業システムの構築である。健全な生態系・人間社会の基盤構築に向けたこれらの取組みには、農家・行政・産業・研究者など、さまざまな主体の協働が不可欠である。各地の先進的な事例をご報告いただき、その後、学生を交えたディスカッションを行いたい(テキストとして鷲谷いづみ編著「コウノトリの贈り物-自然共生社会と生物多様性農業をデザインする(仮)」(地人書館)を使用する。テキストは当日会場で販売する。また本シンポジウム後、数回のディスカッション・質疑応答を行う予定)。 プログラム 主催者あいさつ 鷲谷いづみ(東京大学大学院農学生命科学研究科) 基調講演: 「コウノトリとともに生きる ~豊岡の挑戦」 中貝宗治(兵庫県豊岡市長) 「地域の持続性と農業のあり方を考える」 【第一部:事例・実践報告】 「水田の農業湿地としての特性を活かす、ふゆみずたんぼ」 呉地正行(日本雁を保護する会 会長) 「『ものがたり』を伝えたい!産直・交流事業で農業の価値観を共有する」 石塚美津夫(ささかみ農業協同組合 販売交流課長) 「コウノトリが地域の力を取り戻す」 佐竹節夫(兵庫県豊岡市コウノトリ共生部 コウノトリ共生課長) 「いのちの見える食と文化の回復へ、食堂業の試み」 橋部佳紀(株式会社アレフ) 「食と農をつなぐパルシステムの産直」 野村和夫(パルシステム連合会) 「北海道における”いのち育む有機農業”の可能性 稲葉光國(NPO法人民間稲作研究所 代表) 【第二部:パネルディスカッション・質疑応答】 閉会挨拶 鷲谷いづみ(東京大学大学院農学生命科学研究科 (※演題はすべて仮) ◆対象 上記の授業は修士課程および博士課程の学生を対象にした農学生命科学研究科の共通科目です。研究科共通科目の単位は、研究科の規定により課程修了に必要な単位として加えることができますので、便覧等で条件を確認してください。 ◆受講登録方法・登録受付日 受講を希望する学生は平成19年10月15日(月)~10月19日(金)に学生サービスセンター内の大学院学生担当で受講登録を行ってください。 ◇問合せ先 内容に関して: 保全生態学研究室 菊池玲奈 5841-8915 履修に関して: 産学官民連携室まで

シンポジウム「生物多様性と農業」(ACT12) 日時:2006年11月25日(土)10:00~18:00 場所:東京大学農学部弥生講堂 一条ホール アグリコクーン生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 平成18年度 冬学期 農学生命科学研究科 大学院 共通科目(演習:1単位) 経済性と効率のみの追求による農業形態の変化の中で、急速に不健全化を進めた農業生態系。 その中で、社会と生態系を再生し、自然と調和のとれた人間社会を築こうとする流れは、世界的潮流である。日本でもその萌芽が見られはじめている。2005年11月、ウガンダで開催された第9回ラムサール条約締結国会議において、世界有数のマガンの越冬地である宮城県「蕪栗沼・周辺水田」が条約登録湿地となった。「水田」を明確に湿地として位置づけ、保全対象としたのは、世界にも類をみない画期的事例である。また同年9月には、兵庫県豊岡市において、農業生態系の頂点に位置する「コウノトリ」が、野生復帰に向けて放鳥された。 これらの取り組みの中核を担うのが、生物多様性の保全と矛盾しない新しい農業システムの構築である。健全な生態系・人間社会の基盤構築にむけたこれらの取組みには、農家・行政・産業・研究者など、さまざまな主体の協働が不可欠である。各地の先進的な事例をご報告いただき、その後、学生を交えたディスカッションを行いたい。 プログラム イントロダクション 鷲谷いづみ(東京大学大学院農学生命科学研究科) 基調講演: 「コウノトリとともに生きる ~豊岡の挑戦」 佐竹節夫(豊岡市コウノトリ共生部コウノトリ共生課長) 各地で進む「人と自然の共生」に向けた取組み 「ふゆみずたんぼ(宮城県・旧田尻町ほか)」 呉地正行(日本雁を保護する会 会長) 「魚のゆりかご水田プロジェクト(滋賀県・琵琶湖)」 田中茂穂(滋賀県 農林水産部) 「地域づくりとしての循環型農業(新潟県・旧笹神村」 石塚美津夫(ささかみ農業協同組合) 「人と自然の共生を目指した農業」の農学的立場からの可能性 「株式会社アレフの取組み」 庄司昭夫(株式会社アレフ 代表取締役) 「生き物調査が世界を変える」 原耕造(全農SR推進事務局長) 「パルシステムの産直活動」 田崎愛知郎(パルシステム連合会) パネルディスカッション ◆対象 上記の授業は修士課程および博士課程の学生を対象にした農学生命科学研究科の共通科目です。研究科共通科目の単位は、研究科の規定により課程修了に必要な単位として加えることができますので、便覧等で条件を確認してください。 ◆受講登録方法・登録受付日 履修を希望する学生は平成18年10月16日(月)~10月20日(金)に学生サービスセンター内の大学院係で受講登録を行ってください。 ◆募集人数 50名 ◇問合せ先 内容に関して: 保全生態学研究室 菊池 履修に関して: 産学官民連携室まで

「自然再生がめざすもの」(ACT5) 日時:2006年5月13日(土)13:30~17:00 場所:農学部1号館8番講義室 主催:東京大学21COE生物多様性・生態系再生研究拠点 財団法人 農学会 東京大学農学生命科学研究科 13:30~13:40主催者のあいさつ(COE、農学会) 13:40~14:10小野寺 浩(順応的管理グループ)「自然再生の理念と政策」 14:10~14:50鬼頭 秀一(順応的管理グループ)「環境倫理と自然再生」 14:50~15:20鷲谷 いづみ(拠点リーダー)「自然再生をめぐる世界の動き」 15:20~15:50宮崎 毅(研究理念ワーキンググループ)「自然再生研究とは何か」 15:50~16:10―休憩― 16:10~17:00コメントと会場を交えた討議 司会:鷲谷 いづみ コメンテーター:拠点サブリーダー(武内 和彦、宝月 岱造、西田 睦)










