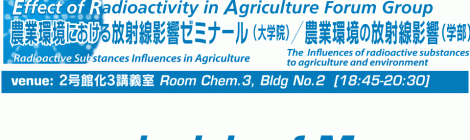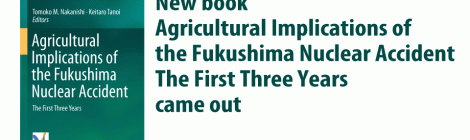
福島原発事故による放射能汚染が農業に及ぼす影響についてまとめた本の第2弾が出版されましたAgricultural Implications of the Fukushima Nuclear Accident(Tomoko M. Nakanishi & Keitaro Tanoi, eds.) に続く、本研究科の成果をまとめた本が出版されました。 下記リンクからオープンアクセスでご覧になれます。 http://link.springer.com/book/10.1007/978-4-431-55828-6HighlightsDetails radioactive contamination in the agricultural systems affected by falloutProvides radioactivity counting data that is easy to understandIntroduces a novel technique to visualize actual movement of cesium in soil and plantsThis book reports the results from on-site research into radioactive cesium contamination in various agricultural systems affected by the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident that occurred in March 2011. This is the second volume from the research groups formed in the Graduate School of Agricultural and Life Sciences of The University of Tokyo who have published the initial data in their first volume. In…
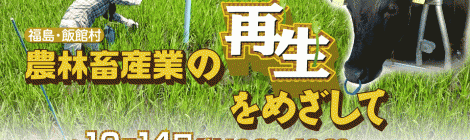
ふくしま再生の会 活動報告会農林畜産業の再生をめざして 東日本大震災後の原発事故から4年半が過ぎました。人間の行為により破壊された飯舘村を取り戻すために何ができるのか。生活と産業の再生をめざす村民、全国からのボランティア・専門家が連携して活動を続けています。それぞれの立場から再生について語ります。 poster(PDF) 日時:2015年10月14日(水)16:00~18:30 場所:東京大学農学部(弥生キャンパス)弥生講堂アネックス1階セイホクギャラリー アクセス: 主催:認定NPO法人ふくしま再生の会 共催:東京大学農学生命科学研究科アグリコクーン農における放射線影響FG(act97) 福島復興農業工学会議 お問合せ:「ふくしま再生の会」事務局 e-mail: desk[at]fukushima-saisei.jp Tel. 03-6265-5850 プログラム 挨拶 東京大学大学院農学生命科学科長・農学部長丹下 健 報告 全体活動報告 認定NPO法人ふくしま再生の会 理事長田尾陽一 飯舘村の生活と農業の再生に向けて ふくしま再生の会理事・飯舘村農業委員会会長菅野宗夫 飯舘村の畜産の再生に向けて 関根・松塚行政区復興委員長山田猛史 飯舘村の農業再生の構想 ふくしま再生の会理事・東京大学福島復興農業工学会議溝口 勝 司会:認定NPO法人ふくしま再生の会 副理事長 大永貴規 懇親会(午後6時45分~午後8時) アグリコクーンでは過去に飯舘村の現地調査を実施しています。 http://www.agc.a.u-tokyo.ac.jp/info/pdf/121005_fg6.pdf http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/lecture/agc-info/12/ また、次の資料もご覧ください。 地域社会と専門家の連携 -大学にできること- http://www.a.u-tokyo.ac.jp/rpjt/event/20130810slide6.pdf
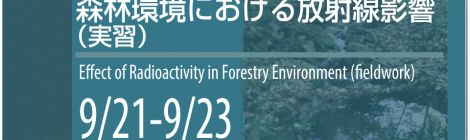
2015年度 森林環境における放射線影響 日程:2015年9月21日(月)〜23日(水) 場所:福島県伊達市霊山町小国 内容: 森林プロットにおける毎木調査(成長量調査) 植物試料サンプリング(伐倒調査) 動物試料サンプリング(昆虫、土壌動物等) 渓流・河川水サンプリング 集合・解散:9月21日(月) 午前8時 東京大学農学部3号館前 集合(地下鉄南北線「東大前駅」より徒歩3分 9月23日(水) 夕刻 東京大学農学部3号館前 解散 参加費:5000円/人(移動・朝昼夕・宿泊費込み) 宿泊先:伊達市霊山町「霊山トレーニングセンター」サマーキャンプ施設 服装:野外活動できる服装。長靴(なければ現地付近で購入可能) 問い合わせ:uktanoi[at]mail.ecc.u-tokyo.ac.jp (RI・田野井) 応募の〆切:未定(履修登録する場合は9/14〜9/25の間にA1タームの授業として履修登録してください)
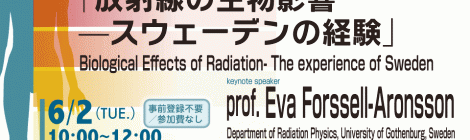
「放射線の生物影響 —スウェーデンの経験」 チェルノブイリ原発事故の影響を大きく受けたスウェーデンでは、環境放射線に関する知見が豊富に蓄積されています。最も汚染された地域のCs-137蓄積量は10万ベクレル/m2にも及び、国を挙げて、外部被ばくの算定にも尽力してきました。また、トナカイを食する遊牧人の内部被ばく量は、事故発生から1年後に最大に達するなど、食の安全に関する多くの知見が得られています。こうした背景の中、長年放射線のリスクについて研究されているEva Forssell-Aronsson教授をお招きして、放射線と生物影響について議論したいと思います。 poster(PDF) 講演:
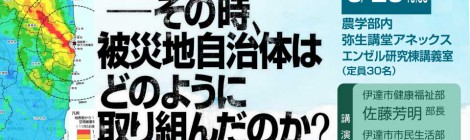
農業の放射線被害-その時、被災地自治体はどのように取り組んだのか? 福島原発事故に伴う農業被害において、各地方自治体はどのような問題をかかえ、どのような取組をされてきたのでしょうか。事故から4年が経過した現在、改めて振り返るとともに、今後の危機対応の参考とすべく、地方自治体でその当時、農業部門の指揮を取っていた方をお迎えしてセミナーを開きます。幅広い方のご参加を歓迎いたします。特に、将来行政職を希望する学生の積極的な参加を期待しています。 poster(PDF) 講演: 佐藤 芳明 氏(伊達市健康福祉部 部長) 斎藤 義則 氏(伊達市市民生活部 部長) 事前登録不要/参加費なし 日時:2015年5月29日(月)16:00~18:00 場所:東京大学弥生キャンパス農学部弥生講堂アネックスエンゼル研究棟講義室(定員30名) アクセス:

Effect of Radioactivity in Agriculture Forum Group Participant Recruitment: Japanese-Swedish Radioecology Workshop Practical education program for radiation related to agricultural environment and food safety, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo Effect of Radioactivity in Agriculture Forum Group, AGRI-COCOON, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo Our faculty, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, will organize a workshop at Stockholm University of Sweden in coming 1st-6th September. Sweden is known as a fist country which detected abnormal amount of radioactive materials and started investigation, except USSR that is a country responsible for nuclear meltdown at Chernobyl, at…
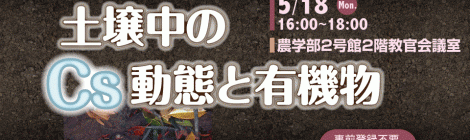
土壌中のCs動態と有機物 福島第一原発事故による放出された核種のうち農林水産業に最も影響を及ぼしている放射性セシウム(Cs)は、一端土壌に接すると動きにくいことが知られています。一方で、有機物が豊富な土壌では、Csが粘土鉱物に固定される前に有機物と接する機会が多く、その挙動は有機物のふるまいと関連しうることが考えられます。今回は、環境地水学研究室の西村拓先生、放射線環境工学研究室の二瓶直登先生、森林理水及び砂防工学研究室の小田智基先生の各位より土壌中のCs挙動と有機物の関係について情報提供をいただき、土壌中Cs動態について分野を超えた議論を深く掘り下げる機会を設けたいと思います。土壌を研究対象とする方のみならず、環境中の放射性Csに興味のある幅広い方の参加を歓迎します。 poster(PDF) 話題提供: 西村 拓 教授(環境地水学) 二瓶 直登 准教授(放射線環境工学) 小田 智基 助教(森林理水及び砂防工学) 事前登録不要/参加費なし 日時:2015年5月18日(月)16:00~18:00 場所:東京大学弥生キャンパス農学部2号館2階教官会議室 アクセス: 主催:東京大学大学院農学生命科学研究科アグリコクーン農における放射線影響FG(act92) 内容: 趣旨説明の後、西村先生、二瓶先生、小田先生より、20〜30分程度で当該テーマに関する情報提供をいただき、質疑応答および総合的議論を行います。 問合先: 田野井慶太朗 uktanoi[at]mail.ecc.u-tokyo.ac.jp (ext.28496)
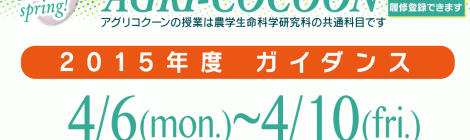
2015年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月7日(火)18:45~ 1号館2階8番講義室 FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月8日(水)17:00~18:00 7号館B棟231・232号室 FG3: 農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ4月10日(金)16:50~ 2号館1階化学2番講義室 FG4: 生物多様性・生態系再生フォーラムグループガイダンスは実施しません。全体ガイダンスで資料を配布します。 FG5: 農学における情報利用研究フォーラムグループ 4月8日(水)16:00~16:307号館B棟231・232号室 FG6: 農における放射線影響フォーラムグループ4月6日(月)18:45~20:30 2号館1階化3講義室 アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG) ◆食の科学フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の向上と豊かな社会の構築を目指します 食の安全・安心の確立と健康社会の構築をめぐる理論と実践を学びます。そこでは高齢社会における課題解決についても考えていきます。例年、講義・演習・実習には100名以上の学生が参加しています。またフォーラムグループの教員もメンバーになっている「食の安全研究センター」と研究と教育の連携を図ります。教育カリキュラムでは専門性と学際性を重視して、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を、地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。6つのサブグループ:「土と文化」「森と文化」「水と文化」「生き物と文化」「農業技術と文化」「プロジェクト実践研修」から成り、各サブグループの活動を、大学院生が中心となって企画・運営します。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します 生物が生産する有機資源であるバイオマスは、農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場に存在しています。バイオマスの高い次元での有効利用、地球環境の持続性を視野に入れたバイオマス利活用で、農学生命科学の研究分野の大きな使命である真の循環社会の構築を目指します。当フォーラムグループでは、この理念にのっとり、バイオマス利活用の現場視察を含むセミナー形式の講義とバイオマス利活用に必要な情報科学に関する演習を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 環境を再生する協働活動を進めます 当FGは、2003年に21世紀COEプログラムの一環で立ち上げられた「生物多様性・生態系再生研究拠点」をベースにしています。さまざまな主体との協働プロジェクトやセミナーの開催などの実績があり、その成果を教育プログラムに還元するとともに、生物多様性とその保全に関わる学際的な新しい科学の創造を目指します。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 最先端農業システムやリモートセンシング・地理空間情報、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う農業気象情報や食料需給問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催し、農業環境情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 放射能汚染地域の大半は農林畜水産業の場です。被災地での農業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科では事故直後から調査研究を行っています。そこで得られた最新の知見や発見に基づく教育プログラムを通じて、農における放射性物質動態・影響を学びます。本FGでは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の輩出を目指します。
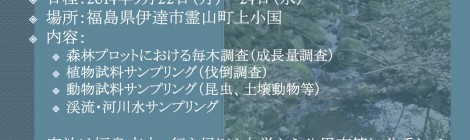
[日程]: 2014年9月22日(月)〜24日(水) 場所: 福島県伊達市霊山町小国 内容: 森林プロットにおける毎木調査(成長量調査)、 植物試料サンプリング(伐倒調査)、 動物試料サンプリング(昆虫、土壌動物等)、 渓流・河川水サンプリング 集合: 後日アナウンスします。 参加費: 後日アナウンスします。食費は自己負担。 服装: 野外活動できる服装。長靴(なければ現地付近で購入可能) 問い合わせ: nobu[at]fr.a.u-tokyo.ac.jp (森林科学・大手) uktanoi[at]mail.ecc.u-tokyo.ac.jp (RI・田野井) 応募の〆切: 9月上旬(募集は締め切らせていただきました)