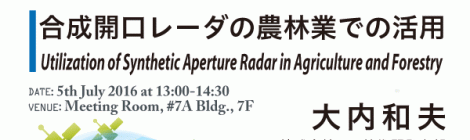
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 合成開口レーダの農林業での活用Utilization of Synthetic Aperture Radar in Agriculture …
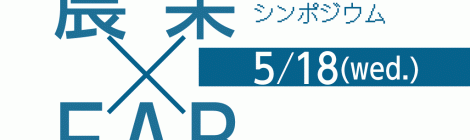
農業×FAB コーディネーター:平藤雅之(農研機構/筑波大学) 農業においては現場の環境や作物・品種などの違いに応じて、計測・制御機器、農業機械等のカスタマイズやちょっとした道具の制作が必要になることがしばしばあります。…

2016年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月7日(木)18:45~ 1号館2階8番講義室 FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月7日(水)17:00~18:00 7号館B棟2…
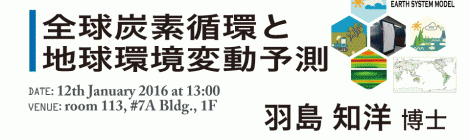
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 全球炭素循環と地球環境変動予測 poster(PDF) 講師:羽島 知洋 博士 国立研究開発法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC)技術研究…
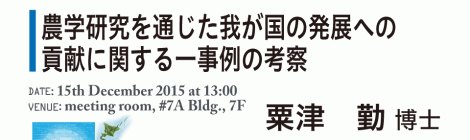
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 農学研究を通じた我が国の発展への貢献に関する一事例の考察 poster(PDF) 講師:粟津 勤 博士 文部科学省 研究開発局 参事官付 専…
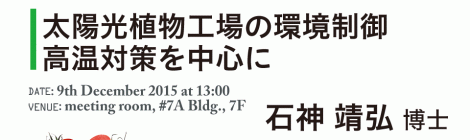
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 太陽光植物工場の環境制御:高温対策を中心に poster(PDF) 講師:石神 靖弘 博士 千葉大学大学院園芸学研究科 生物資源科学コース生…
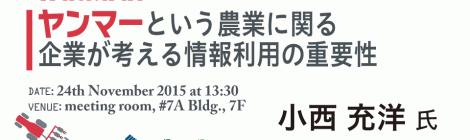
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール ヤンマーという農業に関る企業が考える情報利用の重要性 poster(PDF) 講師:小西 充洋 氏 ヤンマー(株)研究開発ユニット バイオイ…
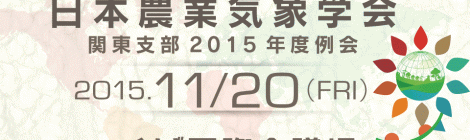
日本農業気象学会関東支部2015年度例会を、下記の要領で開催いたします。本年度は、つくば国際会議場にて総会、一般講演を行う予定です。 当日は支部例会の後、同じ会場内で農業環境技術研究所主催の第29回気象環境研究会が開催さ…
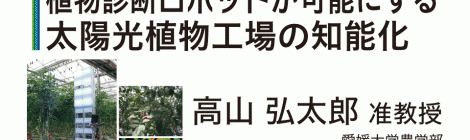
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 植物診断ロボットが可能にする太陽光植物工場の知能化 poster(PDF) 講師:高山 弘太郎 准教授 愛媛大学農学部 施設生産システム学専…
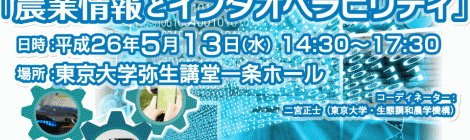
農業情報とインタオペラビリティ 農業情報システムをクラウド化しその効率的かつ効果的運用を行うためには、農業情報の相互運用性(インタオペラビリティ)の確保、即ち多様なデータを多様なシステム間で自由に流通させ、 データ資源や…










