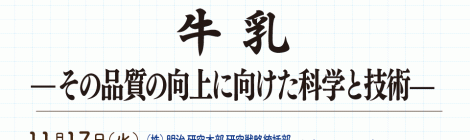
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 牛乳—その品質の向上に向けた科学と技術—/h3> 日時:2020年11月17日(火)19:00〜20:30 教室:zoom(urlはITC-LMSでお知らせ) 講師:(株)明治 研究本部 研究戦略統括部 研究戦略部 研究戦略G G長 神谷 哲 氏 受講にあたってECCSアカウントが必要になりますで、受講前に必ず取得しておいてください。詳細はITC-LMSに記載してあります。 本ゼミナールでは事業者・研究機関における食の安全や健康社会の構築に係る実務や研究活動等について講義いただき、受講生と討議します。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。下記のフォームより登録してください。
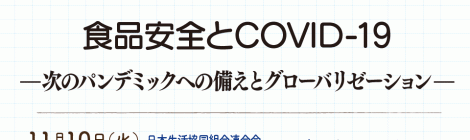
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 食品安全とCOVID-19—次のパンデミックへの備えとグローバリゼーション— 日時:2020年11月10日(火)19:00〜20:30 教室:zoom(urlはITC-LMSでお知らせ) 講師:日本生活協同組合連合会 品質保証本部総合品質保証担当 鬼武 一夫 氏 受講にあたってECCSアカウントが必要になりますで、受講前に必ず取得しておいてください。詳細はITC-LMSに記載してあります。 本ゼミナールでは事業者・研究機関における食の安全や健康社会の構築に係る実務や研究活動等について講義いただき、受講生と討議します。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。下記のフォームより登録してください。
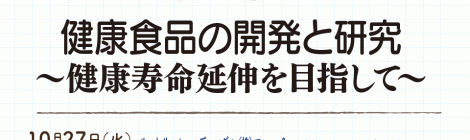
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 健康食品の開発と研究 〜健康寿命延伸を目指して〜 日時:2020年10月27日(火)19:00〜20:30 教室:zoom(urlはITC-LMSでお知らせ) 講師:サントリーホールディングス(株)フェロー& サントリーウエルネス(株) 健康科学研究所長 柴田 浩志 氏 受講にあたってECCSアカウントが必要になりますで、受講前に必ず取得しておいてください。詳細はITC-LMSに記載してあります。 本ゼミナールでは事業者・研究機関における食の安全や健康社会の構築に係る実務や研究活動等について講義いただき、受講生と討議します。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。下記のフォームより登録してください。
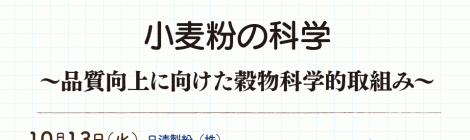
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 小麦粉の科学~品質向上に向けた穀物科学的取組み~ 日時:2020年10月13日(火)19:00〜20:30 教室:zoom(urlはITC-LMSでお知らせ) 講師:日清製粉(株) つくば穀物科学研究所 所長 早川 克志 氏 受講にあたってECCSアカウントが必要になりますで、受講前に必ず取得しておいてください。詳細はITC-LMSに記載してあります。 本ゼミナールでは事業者・研究機関における食の安全や健康社会の構築に係る実務や研究活動等について講義いただき、受講生と討議します。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。下記のフォームより登録してください。
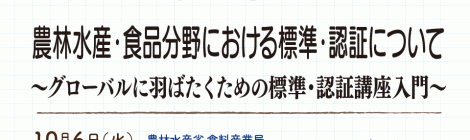
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 農林水産・食品分野における標準・認証について ~グローバルに羽ばたくための標準・認証講座入門~ 日時:2020年10月6日(火)19:00〜20:30 教室:zoom(urlはITC-LMSでお知らせ) 講師:農林水産省 食料産業局 食品製造課 基準認証室 室長 西川 真由 氏 受講にあたってECCSアカウントが必要になりますで、受講前に必ず取得しておいてください。詳細はITC-LMSに記載してあります。 本ゼミナールでは事業者・研究機関における食の安全や健康社会の構築に係る実務や研究活動等について講義いただき、受講生と討議します。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。下記のフォームより登録してください。
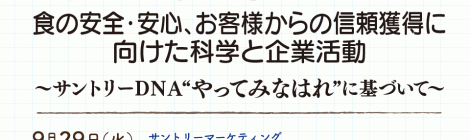
食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 食の安全・安心、お客様からの信頼獲得に向けた科学と企業活動 ~サントリーDNA“やってみなはれ”に基づいて〜 日時:2020年9月29日(火)19:00〜20:30 教室:zoom(urlはITC-LMSでお知らせ) 講師:サントリーマーケティング&コマース(株) 品質保証推進部 技術顧問 冨岡 伸一 氏 受講にあたってECCSアカウントが必要になりますで、受講前に必ず取得しておいてください。詳細はITC-LMSに記載してあります。 本ゼミナールでは事業者・研究機関における食の安全や健康社会の構築に係る実務や研究活動等について講義いただき、受講生と討議します。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。下記のフォームより登録してください。

食の科学FG 夏休み実地研修(食の科学ゼミナールⅡ・食と健康システム演習) 日清食品ホールディングス株式会社 グローバルイノベーション研究センター 暫定版ポスター(PDF) これまで本プログラムは、食品事業者の研究所や事業所を実際に訪問して、研究開発または安全・品質管理の取り組みに関する研修を行ってきました。本年は、新型コロナウイルス感染症対策として、オンラインでの研修としました。ただし、訪問先のご協力により、オンラインでですがこれまで通り、若手研究者とのグループディスカッションが実現しました。学生の皆さんの積極的な参加を期待しています。 なお、食の科学ゼミナールⅡ・食と健康システム演習を履修し、本プログラムに参加しレポートを提出した学生には、出席ポイント3が割り振られます。 日時:2020年9月3日(木)午後15:00〜17:00 場所:Web開催 緊急連絡先:03-5841-8882(アグリコクーン産学官民連携室) プログラム(予定): ・センターの概要説明 ・若手研究員とのグループミーティング (①塩味受容体研究、②乳酸菌研究・製品開発、③培養肉研究(東大-日清の共同研究関連)の3グループ) 定員: 30名 応募締め切り日: 8月24日(月)17時 その他: ・科目履修者の先着順とし、定員に余裕がある場合に非履修者の先着順とします。 ・履修者、非履修者にかかわらず、参加者全員にレポート提出が義務づけられます。 ・申し込んでいて都合が悪くなった場合は、分かった時点で必ずアグリコクーン産学官民連携室に連絡をください。 ・事前にキャンセルが出た場合、落選した申込者に参加を打診する場合があります。 下記のメールフォームよりお申し込みください。注意事項をよく読んで、承諾のチェックボタンを押してください。 ①専修名・専攻、②氏名、学生番号・学年、③履修の有無、④PCのメールアドレス、⑤連絡のとれる電話番号、⑥この研修に期待すること ■応募したにも係わらず、やむをえずキャンセルされる場合は、アグリコクーン産学連携室まで事由も含め応募締切日までに連絡してください。■履修の有無に関わらず、後日レポートを提出していただきます。■非履修生の参加は農学生命科学研究科・農学部の所属に限らせていただきます。■当日のTEAMSの招待メールは参加者に個別に連絡します。また、招待メールの内容は他者に知らせないでください。■オンライン参加で知り得た情報は、参加者内でとどめるようにしてください。 ■参加中の録画、録音、撮影、スクーンショットは禁止します。 レポート課題 9月14日正午までにITC-LMS経由でレポートを提出してください。 履修、非履修にかかわらず、参加者全員にレポート提出を義務づけています。
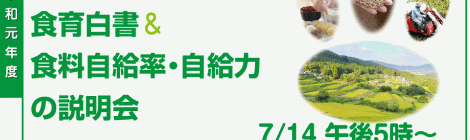
令和元年度 食料・農業・農村白書&食育白書&食料自給率・自給力の説明会 例年開催している「食料・農業・農村白書&食育白書&食料自給率・自給力の説明会」を今年度はオンラインで開催する予定です。 学部・専攻・専修問わずご参加いただけます。 また食の科学ゼミナールⅡの授業としても開講しますので、詳細はメーリングリスト等でアナウンスします。 (7/15追記)OEGs候補生の履修生にはオンデマンド形式で動画を用意しておりますが,google drive上の処理に時間がかかっております.暫くお待ちください. 動画の視聴が可能になりました poster(PDF) 日時:7月14日(火)17:00-18:30 場所:zoom 主催:東京大学大学院農学生命科学研究科アグリコクーン食の科学FG(act132) 事前登録先:受付終了 レポート提出フォーム: CLOSED プログラム 食育白書 (質疑:5分) 農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課 食育計画班 課長補佐西尾 素子 氏 「食料自給率と食料自給力指標について」(質疑:5分) 農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室 企画官井上 崇 氏 食料・農業・農村白書(質疑:10分) 農農林水産省大臣官房広報評価課情報分析室 前課長補佐武藤 明子 氏
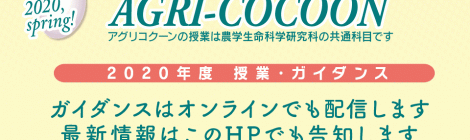
2020年度アグリコクーンガイダンス一覧 まだ情報は掲載されていませんが、オンラインガイダンスのurlは後日掲載します。 研究科website「オンライン授業」の項目も随時確認ください. FG1: 食の科学フォーラムグループ4月7日(火)18:45~ 2号館1階化3講義室PDFファイル掲載(4.13) FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月7日(火)14:00~14:30配布資料 7号館B棟231・232zoomライブ配信 FG3: 農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ4月10日(金)16:45~練習のためzoomでリアルタイムで行います リアルタイムzoom配信(urlはシラバスに掲載.MLに登録してください) FG4: 生物多様性・生態系再生フォーラムグループ6月以降にガイダンス実施予定、状況をみてzoomによるライブ配信などに切り替え FG5: 農学における情報利用研究フォーラムグループ 4月7日(火)17:00~7号館A棟7階会議室youtube配信https://youtu.be/0CZdT9gg84A FG6: 農における放射線影響フォーラムグループyoutube https://youtu.be/Ez01BghyiRc Writing a Research Proposal / Writing a Research Article 4月2日(木)16:00〜16:30 7号館B棟236/237youtubehttps://youtu.be/LG-srhXtmJI アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG) ◆食の科学フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の向上と豊かな社会の構築を目指します 食の安全・安心の確立と健康社会の構築をめぐる理論と実践を学びます。そこでは高齢社会における課題解決についても考えていきます。またフォーラムグループの教員もメンバーになっている「食の安全研究センター」と研究や教育の連携を図ります。教育カリキュラムでは専門性と学際性を重視して、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。「国際農業と文化ゼミナール」では 「環境と農業」 「農業と資源」 「経済と食品流通」の3つのテーマの集中講義と、教員とのディスカッションで農業と文化への理解を深めます。「国際農業と文化実習」では、国内実習により日本の農家と農村について体験的に理解を深めた上で、アジア途上国における実習により、地域における問題の把握やそれらの問題解決のためのプロジェクト形成について経験を積みます。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します バイオマスとは、生物が生産する循環可能な有機資源を意味しています。また、バイオマスは農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場あるいはそれらの下流に位置づけられる産業や社会の中に存在しています。 農学生命科学の研究分野の中で、これらのバイオマスの多面的で高い次元での有効利用、地域環境の保全などを視野にいれた利活用の実現に向けた教育と研究を推進することが、バイオマス利用研究FGの使命と言えます。この理念にのっとり、バイオマス利用研究FGが主催する講義では、セミナー、現場視察、さらに演習を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 生態系や生物多様性を再生する協働活動を進めます 生物多様性の保全や健全な生態系の再生は、さまざまな生態系サービス(自然の恵み)の提供を通して、地域社会の持続可能性に貢献するものです。地域における自然再生や生態系管理にとって、地域の多様な関係者との協働は大きな役割を持っており、さまざまな地域で実践活動が進んでいます。国内の先進的な事例をとりあげ、地域と連携した実習などにより、自然再生や生態系管理について実践的に学びます。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 最先端農業システムやリモートセンシング・地理空間情報、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う農業気象情報や食料需給問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催し、農業環境情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 福島第一原発事故による放射能汚染地域の大半は、農林畜水産業の場です。この被災地における農林畜水産業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科は事故直後からそのための調査研究を行っています。本FGでは、最新の知見や発見に基づく教育プログラムによって、農における放射性物質の動態や影響を学びます。本FGは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の育成を目指します。
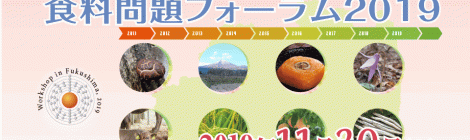
東日本大震災に係る食料問題フォーラム2019 開催趣旨: 東日本大震災によって引き起こされた東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故により、福島県を中心に大量の放射性物質が環境中へ放出され、食料資源の生産現場にも大きな被害をもたらした。この事故からすでに8年が経過し、福島産の農林水産物についても安全モニタリングの普及や自主検査などにより、市場には厳しい安全規制をクリアした食品しか流通していないが、消費者は福島県産の食品に未だ不安を抱いている。そこで本フォーラムでは、事故からの8年を振り返り、いかにして福島県産の食品の安全性を消費者に理解してもらうことができるのか、農林水産業の現場における活動および食品の流通から食卓までの安全の取り組みを議論し、福島県農林水産業復興の加速に資することを目指す。 poster(PDF) 日時:令和元年11月30日(土) 13:00〜17:00 場所:福島大学 L4教室(福島県福島市金谷川1番地) 主催:日本学術会議農学委員会・食料科学委員会合同東日本大震災に係る食料問題分科会、国立大学法人福島大学 後援:日本農学アカデミー、公益社団法人日本水産学会、公益社団法人日本畜産学会、日本農業経済学会、公益社団法人日本農芸化学会、農業食料工学会、公立大学法人福島県立医科大学、国立大学法人長崎大学福島未来創造支援研究センター、国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科アグリコクーン(act129)、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、福島県、GAP普及推進機構 参加費・申込:参加無料/事前登録不要 次第: 司会:西澤 直子(日本学術会議連携会員、石川県立大学学長) 13:00〜13:20 開会挨拶 澁澤 栄(日本学術会議第二部会員、東京農工大学大学院農学研究院教授) 生源寺 眞一(日本学術会議連携会員、福島大学食農学類教授・学類長) 13:20〜14:00 発災から8年余りを振り返る: 福島大学うつくしまふくしま未来支援センターの取り組み初澤 敏生(福島大学人間発達文化学類教授、うつくしまふくしま未来支援センター長)飯舘村で「までいの心」を綴る杉岡 誠(飯舘村復興対策課農政第一係長) 14:00〜15:00 水農林漁業復興の現場から: 福島の農業再生における課題・成果・展望石井 秀樹(福島大学食農学類准教授)森林の放射性セシウムの動態と生態学的経済再生金子 信博(福島大学食農学類教授・評議員)魚類の放射能汚染の現状と漁業復興への課題和田 敏裕(福島大学環境放射能研究所准教授) 15:00〜15:40 流通から食卓まで: 食の安全安心確保とふくしまの今!菅野 孝志 (福島県農業協同組合中央会会長) 原発事故後の放射性物質の現状と対応~生産現場から食卓まで~ 八戸 真弓(農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門ユニット長) 15:40〜16:10 休憩および関連研究成果の展示 16:10〜16:50 総合討論 初澤 敏生/杉岡 誠/石井 秀樹/金子 信博/和田 敏裕/菅野 孝志/八戸 真弓 司会:中嶋 康博(日本学術会議連携会員、東京大学大学院農学生命科学研究科教授) 16:50〜17:00 閉会の挨拶 眞鍋 昇(日本学術会議第二部会員、大阪国際大学学長補佐・人間科学部教授) お問い合わせ先 東京大学農学生命科学研究科アグリコクーン産学官民連携室 e-mail: office[at]agc.a.u-tokyo.ac.jp tel: 03-5841-8882 fax: 03-5841-8883










