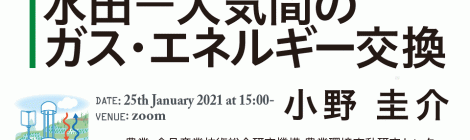
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 水田ー大気間のガス・エネルギー交換 poster(PDF) 講師:小野 圭介 農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 気候…
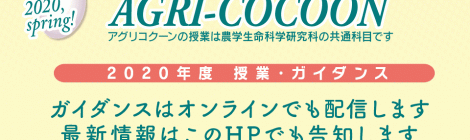
2020年度アグリコクーンガイダンス一覧 まだ情報は掲載されていませんが、オンラインガイダンスのurlは後日掲載します。 研究科website「オンライン授業」の項目も随時確認ください. FG1: 食の科学フォーラムグル…
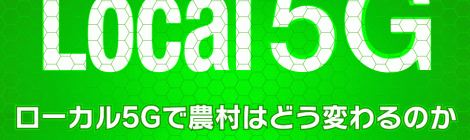
農学における情報利用研究フォーラムグループ ローカル5Gで農村はどう変わるのか—その可能性を考える— poster(PDF) 日時:2020年3月4日(水)11:00-16:30 場所: 東京大学中島董一郎記念ホール(農…
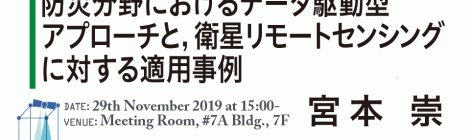
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 防災分野におけるデータ駆動型アプローチと,衛星リモートセンシングに対する適用事例 poster(PDF) 講師:宮本 崇 山梨大学 工学部土…
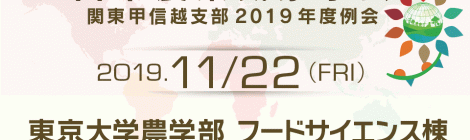
日本農業気象学会 関東甲信越支部2019年度例会 日本農業気象学会関東甲信越支部2019年度例会を、下記の要領で開催いたします。 本年度は、東京大学農学部(弥生キャンパス)で開催いたします。奮ってご参加下さい。 詳しい情…

Joint Student Seminar on Remote Sensing and Geoinformatics 台湾の国立中央大学および東京工業大学とのジョイントセミナーを開催します。奮ってご参加下さい。 post…

農学における情報利用研究フォーラムグループ AI・ディープラーニングを活用したMATLABの農学分野への適用事例 参加者多数につき,教室が変更になりました poster(PDF) 講師:MathWorks Japan 草…
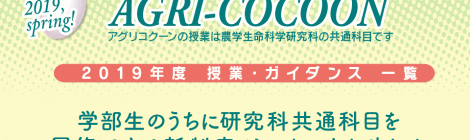
2019年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月4日(木)17:00~17:30 2号館1階化3講義室(合同開催) FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月4日(木)18:15~1…
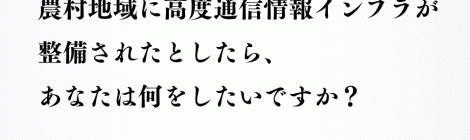
農学における情報利用研究フォーラムグループ 農村地域に高度通信情報インフラが整備されたとしたら、あなたは何をしたいですか?-Society 5.0と農業農村工学- poster(PDF) 飛び込み参加歓迎 日時:平成31…
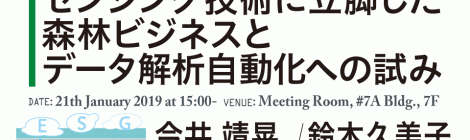
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール センシング技術に立脚した森林ビジネスとデータ解析自動化への試み poster(PDF) 講師: 今井靖晃 国際航業株式会社 森林事業推進チー…










