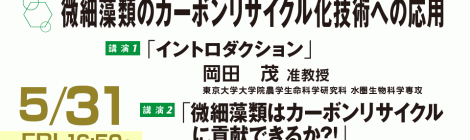
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 日時:2019年5月31日(金)16:50〜18:30 教室:農学部2号館化学2番教室 微細藻類のカーボンリサイクル化技術への応…
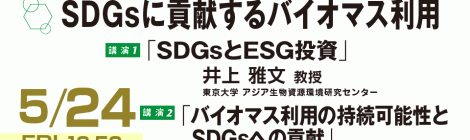
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 日時:2019年5月24日(金)16:50〜18:30 教室:農学部2号館化学2番教室 SDGsに貢献するバイオマス利用 講義 …
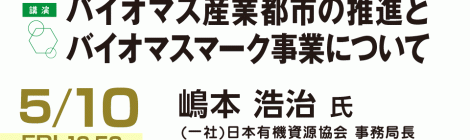
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 日時:2019年5月10日(金)16:50〜18:30 教室:農学部2号館化学2番教室 講義 「バイオマス産業都市の推進とバイオ…
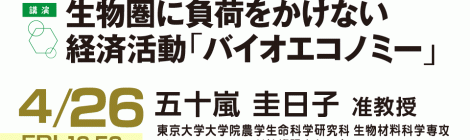
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 日時:2019年4月26日(金)16:50〜18:30 教室:農学部2号館化学2番教室 講義 「生物圏に負荷をかけない経済活動「…
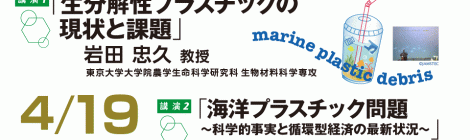
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅱ poster(PDF) 日時:2019年4月19日(金)16:50〜18:30 教室:農学部2号館化学2番教室 講義 「生分解性プラスチックの現状と課題…
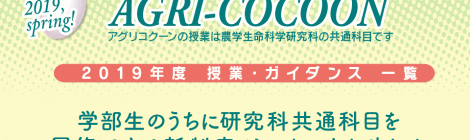
2019年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月4日(木)17:00~17:30 2号館1階化3講義室(合同開催) FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月4日(木)18:15~1…
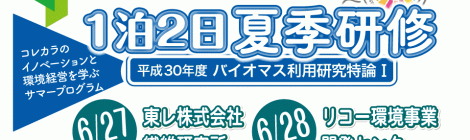
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅰ poster(PDF) 2018年度 1泊2日夏季研修:バイオマス利活用現場の視察、現地セミナーと集中討議 現在、学生・教職員・社会人を対象も参加可能で…
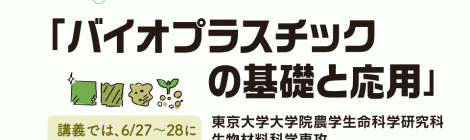
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅰ poster(PDF) 日時:平成30年5月29日(金)16:50〜18:30 教室:農学部2号館化学2番教室 講義 バイオプラスチックの基礎と応用 東…
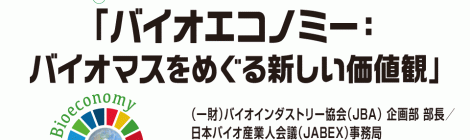
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅰ poster(PDF) 日時:平成30年5月25日(金)16:50〜18:30 教室:農学部2号館化学2番教室 講義 バイオエコノミー:バイオマスをめぐ…
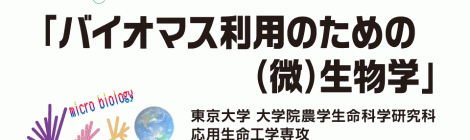
バイオマス利用研究フォーラムグループ > バイオマス利用研究特論Ⅰ poster(PDF) 日時:平成30年5月11日(金)16:50〜18:30 教室:農学部2号館化学2番教室 講義 「バイオマス利用のための(微)生物…










