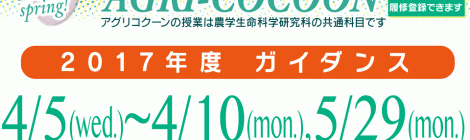
2017年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月6日(木)18:45~ 1号館2階8番講義室 FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月5日(水)18:15~19:00 7号館B棟2…
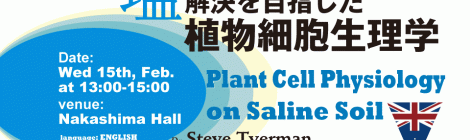
塩類土壌での農業問題の解決を目指した植物細胞生理学 FG6の第3回セミナーを開催します。今回は、オーストラリアの農業上最大の課題である乾燥ストレス・耐塩ストレスに対し、電気生理学・分子生理学を起点として塩害フィールドでの…

Some aspects on radioecology in Sweden, past and present Note: An overview on the history of Swedish radioecol…
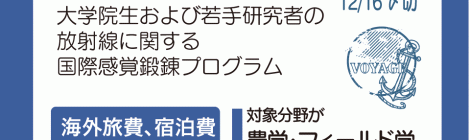
平成28年度 東京大学大学院農学生命科学研究科 教育研究事業 第2回 大学院生および若手研究者の放射線に関する国際感覚鍛錬プログラム 募集要項 今回の募集告知は夏期に募集した「大学院生および若手研究者の放射線に関する国際…
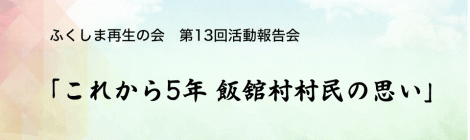
ふくしま再生の会 第13回活動報告会「これから5年 飯舘村村民の思い」 私たち「ふくしま再生の会」は、福島第一原発事故後2011年6月以来5年余にわたり、全村避難中の福島県相馬郡飯舘村において、村民・ボランティア、専門家…
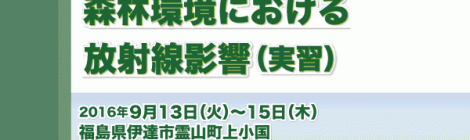
2016年度 森林環境における放射線影響 日程:2016年9月13日(月)〜15日(水) 場所:福島県伊達市霊山町小国 内容: 森林プロットにおける毎木調査(成長量調査) 植物試料サンプリング(伐倒調査) 動物試料サンプ…
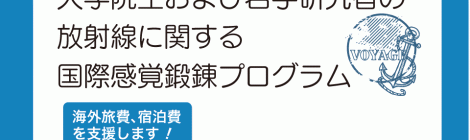
平成28年度 東京大学大学院農学生命科学研究科 教育研究事業 大学院生および若手研究者の放射線に関する国際感覚鍛錬プログラム募集要項 1.概要 農学分野における国際的感覚を備えた課題解決力を持つ人材の養成プログラムの一環…
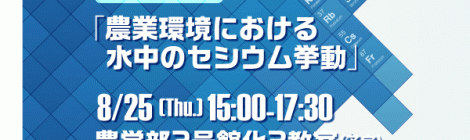
農業環境における水中のセシウム挙動 福島第一原発事故による放出された核種のうち農林水産業に最も影響を及ぼしている放射性セシウム(Cs)は、森林、農耕地へ降下し、用水、河川等へ移行することが知られています。流域内における放…

東京大学農学生命科学研究科では、震災の翌年に福島県飯舘村村長と研究協力の関係を結び、農学生命科学研究科の教職員・学生が飯舘村をはじめとする現地で調査活動をこれまで行ってきました。 今回の企画は飯舘村小宮地区の大久保金一農…

2016年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月7日(木)18:45~ 1号館2階8番講義室 FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月7日(水)17:00~18:00 7号館B棟2…










