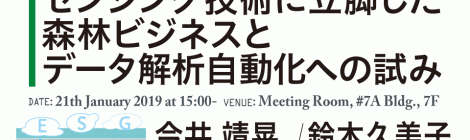
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール センシング技術に立脚した森林ビジネスとデータ解析自動化への試み poster(PDF) 講師: 今井靖晃 国際航業株式会社 森林事業推進チー…
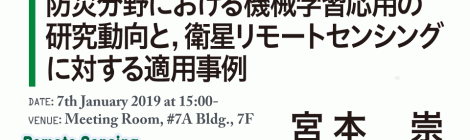
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 防災分野における機械学習応用の研究動向と,衛星リモートセンシングに対する適用事例 poster(PDF) 講師:宮本 崇 山梨大学 工学部土…
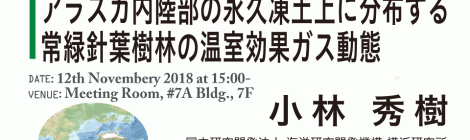
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール アラスカ内陸部の永久凍土上に分布する常緑針葉樹林の温室効果ガス動態 poster(PDF) 講師:小林 秀樹 国立研究開発法人 海洋研究開発…
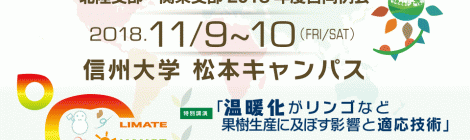
日本農業気象学会 北陸支部・関東支部2018年度合同例会 日本農業気象学会北陸支部・関東支部2018年度合同例会を、下記の要領で開催いたします。本年度は、信州大学松本キャンパスで開催いたします。施設見学会も開催いたします…

農業ICTの次の展開に向けて コーディネーター:亀岡孝治(三重大学) モノのインターネット(IoT)が整備され、日々産み出されるビッグデータをAIが処理するデジタル社会において、地域の生活を豊かにしてくれる「デジタル農…

農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール National Forest Monitoring System of Indonesia poster(PDF) 講師:Yudi Set…

2018年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月5日(木)18:45~ 1号館2階8番講義室 FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月4日(水)18:15~19:00 7号館B棟2…
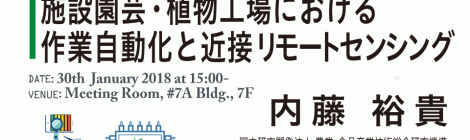
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 施設園芸・植物工場における作業自動化と近接リモートセンシング poster(PDF) 講師:内藤 裕貴 国立研究開発法人 農業・食品産業技術…
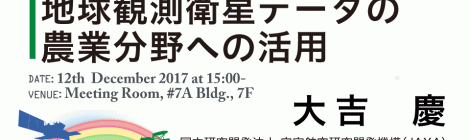
農学における情報利用研究フォーラムグループ > 農学における情報利用ゼミナール 地球観測衛星データの農業分野への活用 poster(PDF) 講師:大吉 慶 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 地球観測研…











